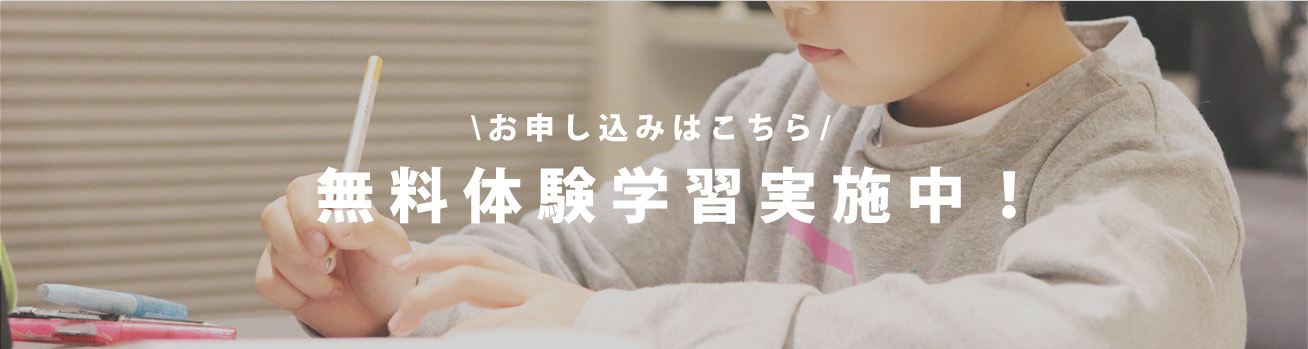近年、子どもへの金融教育の重要性がますます高まっています。
将来のために正しい金融知識を身につけてほしい、と願う親御さんも多いのではないでしょうか。
国も金融教育推進機構(J-FLEC)を設立するなど、金融リテラシー向上に注力しています。
人生に欠かせない金融経済教育で身につく力とJ-FLECについて、詳しく紹介します。
この記事のコンテンツ
金融教育が必要とされている理由

必要性が高まる金融経済教育の背景などについて解説します。
金融経済教育の推進が注目される背景
金融広報中央委員会「金融リテラシー調査2022年」によると、金融教育を受けた認識がある人の割合は全体のわずか7.9%です。
日本人の約9割の人は金融教育を受けた認識がない、という結果です。
金融知識・判断力の平均正答率は全体で55.7%、若年層(18~29歳)では41.2%でした。
年代が上がるほど正答率も高くなることから、若年層の金融知識が不足していることがうかがえるでしょう。
この調査の結果を受けて、国民に正しい金融教育を届けることが急務とされました。
【参照:金融経済教育推進機構(J-FLEC) https://www.j-flec.go.jp/
金融広報中央委員会「金融リテラシー調査2022年」:https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2022/pdf/22literacyr.pdf】
社会の変化とともに高まるお金の知識の重要性
近年、一人ひとりがお金について理解し正しく判断する力が求められるようになっています。
お金の知識の重要性は、以下の社会背景からますます高まっています。
- 少子高齢化にともなう年金不安
- 金融トラブルの低年齢化
- キャッシュレスの普及
- インフレで貯金だけでは安心できない時代
少子高齢化により年金が減額される可能性があるなど、さまざまな年金不安があります。
金融リテラシーの低さから、投資詐欺・借金などの若年層の金融トラブルも増加傾向です。
現代ではキャッシュレスの普及により、お金の価値を実感しにくくなっています。
超低金利の現代では、銀行にお金を預けていてもほとんど利子がつきません。
物価上昇が続くインフレでは、お金の実質的な価値は目減りしていきます。
貯金だけでは安心できないため、これからはお金を増やす力や守る力が求められるでしょう。
「貯蓄から投資へ」の流れもあり、国も資産形成できる仕組みづくりを進めています。
新NISAやiDeCoなどの制度により、国民の長期的な資産形成をサポートしています。
日本の金融リテラシーの低さが子どもの将来に与える影響
金融リテラシーが低いままだと、子どもの将来にさまざまな影響を与える可能性があります。
- お金の不安がつきまとい自由に選択できない
- 将来設計が立てにくくなる
- 金融トラブルに巻き込まれやすい
- 貯金や運用でお金を増やすことができない
進学や就職などでお金の不安がつきまとい、自由に選択できない可能性があります。
また、お金の使い方や貯め方がわからないと、将来設計を立てにくくなります。
金融リテラシーが低いと適切な金銭感覚や正しい情報を見極める力が身についていません。
借金・詐欺などの危険に気づくことができず、金融トラブルに巻き込まれやすくなるでしょう。
資産運用の基本的な仕組みを理解していない人は、投資は怖いものだと思い込み避ける傾向があります。
知識がある人はお金を働かせて増やすことができる一方、知識がない人はお金に振り回される人生を送るなど、金融リテラシーの違いが生活の豊かさに影響を与えます。
金融教育推進機構(J-FLEC)とは?知っておきたい3つの役割

J-FLECは、中立かつ公正な金融経済教育を推進する組織です。
設立の背景と目的などについて解説します。
J-FLECとは?中立・公正な金融教育を推進
J-FLECは2024年4月に設立された金融庁所管の認可法人です。
金融教育の出張イベントやセミナーの開催、個別相談体験、金融を学べる教材・コンテンツの提供を通じて国民の金融リテラシーの底上げに貢献しています。
小学生からシニア層まで、年齢層別の金融リテラシーを習得できるでしょう。
ホームページやYouTubeチャンネルでも、金融経済教育の最新情報が公開されています。
J-FLEC設立の背景と目的
従来では、政府・金融広報中央委員会・金融関係団体のそれぞれが学校や職場などで金融経済教育を実施していました。
しかし、各団体や企業が独自の金融教育を実施していたため、自社の商品・サービスに有利な内容だったり、知識に偏りがあったり、さまざまな課題がありました。
また、2022年に政府が発表した「資産所得倍増プラン」も設立背景のひとつと言えるでしょう。
「資産所得倍増プラン」は、貯蓄から投資への転換を促し、経済成長と家計の豊かさを好循環させることを目的とした政策です。
中立かつ公正な立場からの正しい金融教育を国民に届け、全体の金融リテラシーを向上させる官民一体の組織が必要だったことから、金融広報中央委員会・全国銀行協会・日本証券業協会が発起人となりJ-FLECが設立されました。
経済的・精神的にも安定した生活を送れている状態を指すファイナンシャル・ウェルビーイング実現のための基盤づくりこそが、J-FLEC設立の目的です。
J-FLECについて知っておきたい3つの役割
J-FLECは3つの役割を通して、ファイナンシャル・ウェルビーイング実現を目指します。
- 金融経済教育の提供
- 金融リテラシーの向上
- 金融意識・行動の変容
講師派遣やイベント・セミナー、教材などを通じて、金融経済教育の機会を全国の幅広い年代に提供しており、年間1万回の講師派遣・年間75万人の参加を目標値としています。
金融知識・判断力に関する設問の正答率を70%に引き上げることを目標に掲げ、受講者が正しい金融知識を習得し、適切に判断・活用できる金融リテラシーを向上させる役割があります。
金融経済教育を受けたことで起きる意識・行動の変化では、生活設計などへの意識を持つ割合と外部知見の活用率を10%以上向上させるのが目標です。
【参照:金融教育推進機構(J-FLEC)https://www.j-flec.go.jp/】
日本金融教育支援機構(FAINCATION)の活動と特徴

FAINCATIONは、金融リテラシー向上と金融指導者の育成を推進する民間団体です。
FAINCATIONとは?金融リテラシーの向上を目指す民間団体
FAINCATIONは「人生の選択肢を増やす金融教育を」を掲げる民間団体です。
金融経済教育は、老若男女が社会・経済の仕組みや制度をしっかり理解し、自ら判断・選択する力を身につけられる全世代必須の教養です。
FAINCATIONでは、自立的な安心かつ豊かな人生に重要な金融リテラシーを全国に普及させる取り組みを実施しています。
「お金の8つの力」メソッドによる金融教育
FAINCATIONでは「お金の8つの力」メソッドによる金融教育を提供しています。
お金の力を「使う」「稼ぐ」「納める」「貯める」「備える」「贈る」「借りる」「増やす」の8つに分類しています。
それぞれの切り口からお金の力をわかりやすく伝えるオリジナルメソッドです。
社会とのつながりや人生設計などを考えるきっかけになる学びでしょう。
若者が主体の金融教育イベント「FESコンテスト」を開催
資産形成への意識が高まる一方、適切な金融教育を提供できる人材は十分ではありません。
FAINCATIONでは、中高生が金融教育を実践する「FESコンテスト」の開催などを通じて、金融教育の指導者育成・金融リテラシー向上に努めています。
「教える立場が一番の学びである」というコンセプトのもと、中高生が小学生のために金融教育の動画教材を制作する金融教育動画コンテストです。
小学生にわかりやすく教えることで、お金や経済について主体的に学び理解を深められます。
【参照:日本金融教育支援機構(FAINCATION)https://faincation.com/】
金融経済教育で身につく4つの力!

金融経済教育では、以下の4つの力を身につけられます。
- 家計を管理し計画的にお金を使う力
- 将来のライフイベントを見据えて生活設計する力
- 金融経済を理解し適切な金融商品を選ぶ力
- 正しい情報を選び困ったときには人に相談できる力
それぞれ解説します。
家計を管理し計画的にお金を使う力
家計の収支のバランスを理解し、計画的にお金を使う力を身につけます。
お小遣い帳でお金の流れを見える化し、使い道を振り返ることで価値の判断力を養えます。
お金には限りがあることを実感しやすく、正しい金銭感覚を身につけられるでしょう。
浪費や借金など、将来の金融トラブルのリスクを抑えることにつながります。
将来のライフイベントを見据えて生活設計する力
進学や就職、結婚、住宅、教育、老後など、将来のライフイベントに向けて準備する力です。
いつ・何に・どのくらいお金が必要なのかを、自分で考えられるようになります。
目標に向かって計画を立てることで、お金は夢を実現する手段のひとつと認識できるでしょう。
自分の人生を主体的に選択できる力を育むことができます。
金融経済を理解し適切な金融商品を選ぶ力
金利、インフレ、投資、保険などの仕組みを理解し、目的に合った金融商品を選ぶ力が身につきます。
金融商品はそれぞれ仕組みやリスクが異なるため、適切な商品を見極めることが重要です。
正しい情報を選び困ったときは人に相談できる力
信頼できる情報を見極め活用する力を育てられます。
現代では、SNSやネット、広告など、さまざまな情報が溢れており、誤った情報も少なくありません。
正しい情報なのかを確認する習慣をつけることで、情報に振り回されずに判断できるようになります。
また、困ったときに家族や専門家などに相談する力も大切です。
家庭でできる金融教育と実践的に学べる金融塾

子どもがお金に興味を持ったタイミングで、家庭でも金融教育を始められます。
お小遣い管理を任せてみたり、目標を立てて貯金したり、お金について学ぶことができます。
実践的に学びたい方は、金融塾の活用も選択肢のひとつです。
お小遣い管理・買い物体験でお金の価値を学ぶ
お小遣い管理では、計画的にお金を使う力が育ちます。
お金の使い道を見える化できるため、お金について考える習慣が身につきます。
買い物体験では、お金には限りがあることや欲しいものと必要なものを区別することなど、消費の判断力を鍛えられるでしょう。
目標を立ててコツコツ貯金する習慣を身につける
目標を立ててコツコツ貯金する習慣から、我慢の大切さや達成感を味わうことができます。
計画的にお金を使う力は、将来の家計管理や生活設計の基礎になります。
親子でお金について話す時間をつくる
親子でお金について話す時間をつくることで、自分の生活と社会のつながりを実感できます。
会話で親のお金に対する考え方や価値観、経験を伝えられます。
日常生活のさまざまなテーマを通じて、お金の価値や仕組みを自然に学ぶことができるでしょう。
金融知識をさらに伸ばすなら金融塾での学びも選択肢のひとつ
家庭での金融教育の効果は、親の金融リテラシーに左右される傾向があります。
子どもの金融知識をさらに伸ばしたい方やもっと専門的な知識を学ばせたい方は、金融塾での活用も選択肢のひとつでしょう。
金融塾MIRADASは、学校では教えてくれない経済とお金の本質を学ぶことができるファイナンシャルスクールです。
ディスカッションや投資体験を通じて、経済の仕組み・お金の大切さを主体的に学びお金に強い子を育てます。
まとめ:金融教育で金融リテラシーを高めよう!
自立的な安心かつ豊かな人生において、金融リテラシーは欠かせないスキルです。
金融リテラシーが低いまま大人になるとお金の不安がつきまとい、生活が不安定になる可能性があります。
金融経済の推進機構J-FLECについて知ることで、中立・公正なイベントやセミナー、教材・コンテンツなどを家庭での金融教育に役立てられるでしょう。
子どもの金融知識をさらに伸ばしたい方は、体系的に学べる金融塾の活用もおすすめです。
生きるために欠かせない金融リテラシーを子どものうちに身につけてほしい、という親御さんは、金融塾MIRADASの活用を検討してみてはいかがでしょうか。