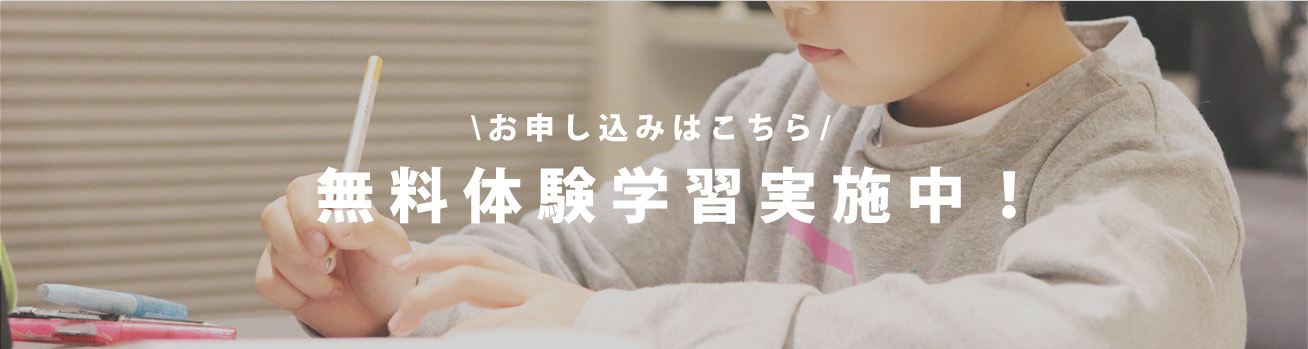「物価が上昇しているのに収入は増えていない」
「年金だけでは老後が不安」
子どもには将来お金に困らない力を身につけてほしい、という親御さんも多いのではないでしょうか。
お金の知識は、将来の選択肢を広げることに役立ちます。
親子で一緒に学べるお金の基本や資産運用の考え方などについて、詳しく紹介します。
この記事のコンテンツ
小学生からの金融教育は早すぎる?注目されている理由と必要性

小学校の授業ではすでに金融教育が取り入れられているため、早すぎることはありません。
小学生から正しいお金の知識を身につけることは、将来の安心や豊かな人生につながります。
お金の教育が注目されている理由
金融教育とはお金の仕組みや使い方・貯め方を知り、経済的な判断を自分でできるようになるための学びです。
金融教育は、子どもの成長や理解度に合わせて段階的に進めることが大切です。
お金の教育によって自己管理能力や意思決定力など、人生のあらゆる場面で必要になる力を身につけられます。
金融庁が推進する早期の金融教育
金融庁では子ども向け金融教育を積極的に推進し、金融経済教育推進機構(J-FLEC)や学校との連携を通じて全国の金融リテラシー向上を支援しています。
子どもへの金融教育は、2022年度の学習指導要領改訂をきっかけに高校では義務化、小中学校でも授業で取り入れる流れになり重視され始めました。
社会の変化とともに高まる金融教育の必要性
社会の変化を背景に、子どもへの金融教育の必要性は一層高まっています。
- キャッシュレスの普及
- 年金不安
- 詐欺被害の低年齢化
- 「貯蓄から投資へ」の流れ
現代ではキャッシュレス化が進み、現金を使わずに買い物できるため、お金の価値や重みを実感しにくくなっています。
現金の支払いでは、お金の単位や計算、使えばなくなることなどを自然に学ぶことができます。
しかし、現代の子どもは、支払い方法の多様化により現金から自然に学べる機会が減っているため、意識的な金融教育が必要です。
また、年金だけでは老後資金が不足したり、詐欺被害が低年齢化していたり、将来的なお金に関する不安があることで金融リテラシーの重要度は増すばかりでしょう。
新NISAやiDeCoは、自助努力で老後資金を準備できるよう「貯蓄から投資へ」の長期的な資産形成をサポートする国の制度です。
親世代が学ばなかったお金の基本と仕組みを紹介

親世代が学校で金融教育を学ぶことは、ありませんでした。
学校の授業で金融教育を取り扱い始めたのは、ごく最近です。
親世代が金融教育を受けていない理由
親世代は、定年まで同じ会社で働き続けることを前提とした終身雇用や年金制度への信頼が高かったため、老後も安心だという考え方が一般的でした。
また、投資は危険なものというイメージがあったため、銀行や郵便局にお金を預ける人が多い時代です。
老後資金を自分で準備する必要性が低い背景から、親世代の学校で金融教育が扱われることはありませんでした。
親子で学べるお金の基本と仕組み
お金は、欲しいものやサービスと交換できる道具です。
お金は働いた対価として得られるため、お手伝いでもらえたお小遣いも収入のひとつだと言えるでしょう。
お金の「使う・貯める・増やす・守る」の4つの力をバランスよく育てることが金融教育では重視されています。
お金を使う力は、必要なものと欲しいものを区別してお金を上手に使う力です。
将来のために少しずつ貯金したり、目標のために我慢したり、計画的にお金を貯める力やお金を増やす仕組み・考え方を知ることも重要です。
小学生のうちから正しい金融知識を身につけることで、だまされずにお金を守る力を高められるでしょう。
金融庁が重視する金融リテラシーとは
金融リテラシーとはお金に関する正しい知識と判断力を指します。
金融庁では、一人ひとりが自立し豊かな人生を築くための生きる力として重視されている要素です。
金融庁は「お金を上手に使う力」「将来に向けた計画を立てる力」「お金の仕組みを知る力」「困ったときに相談する力」を身につけ、お金の知識と考える力を育てることを目指しています。
金融経済教育推進機構(J-FLEC)の「金融リテラシー・マップ」には、年齢や発達段階によって子供から大人までが身につけるべき金融リテラシーが示されているため参考にするとよいでしょう。
金融経済教育推進機構(J-FLEC)は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。
【参照:金融経済教育推進機構(J-FLEC)https://www.j-flec.go.jp/
「金融リテラシー・マップ」https://www.j-flec.go.jp/wpimages/uploads/literacy_map.pdf】
お金の価値は変わる?貯蓄だけでは安心できない理由とインフレの仕組み

貯蓄も大切ですがお金の価値は変わるため、これからはお金の増やす力を高める考え方も重要です。
お金の価値が変わる仕組みを解説します。
貯蓄だけでは資産を守れない?変化するお金の考え方
超低金利な現代では、銀行にお金を預けていてもほとんど利子がつかず、資産は増えていきません。
また、物価上昇が続くとお金の実質的な価値は下がってしまいます。
貯める力ももちろん必要ですが、投資信託や株式などへの投資によりお金を働かせて増やす考え方も重要です。
インフレとは?お金の価値が変わる仕組みを解説
インフレとは、物の値段が上がっていくことです。
現在100円で買えるものが数年後150円になった場合、100円の価値が下がったことになります。
一般的に物価は上昇しお金の価値は下がっていくので、貯蓄だけでは安心できません。
お金の価値は一定ではなく時間とともに変化することやインフレに強い資産への投資など、お金を守る力を身につけることが大切です。
これからはお金を増やす力が求められる
これからは、投資などによりお金を働かせて増やす力が求められます。
国も新NISAやiDeCoなどの制度により、国民の長期的な資産形成をサポートしています。
しかし、投資で必ずお金が増えるとは限りません。
お金が減る可能性もあるため、注意が必要です。
資産形成は、長期的な視点でコツコツ続けることがポイントです。
【小学生向け】お金を働かせるとは?資産運用の基本と考え方

お金を働かせるとは、お金がお金を生み出す仕組みのことです。
お金を効率的に増やす資産運用の基本と考え方を紹介します。
お金を働かせる仕組みと資産運用についてやさしく解説
お金を働かせるとは、お金がお金を生み出す仕組みです。
預貯金や株・投資信託などへの投資により、お金を効率的に増やす資産運用を指します。
お金を銀行に預けて利子を得たり、株式投資で分配金を受け取ったり、お金が増えていく仕組みです。
投資はギャンブル?リスクとリターンのバランスが大切
投資とは、将来的にお金が増えることを期待して自分のお金を投じることです。
投資はお金を増やす方法のひとつなので、ギャンブルとは仕組みが異なります。
しかし、投資にはリスクがあり、必ずお金が増えるとは限らないため注意が必要です。
投資するタイミングによってはお金が減る可能性もあるため、リスクとリターンのバランスを考えて判断することを理解しておきましょう。
親子でお金について話してみよう
親子でお金について話すことも金融教育です。
両親の仕事や家計、買い物、光熱費などについて話すことで、自分の生活とお金のつながりを実感しやすくなります。
ニュースを見ながら親子で話したり、一緒に考えたり、社会や経済への興味を深めるきっかけになります。
時間を味方につける複利の力!お金が増える仕組みを解説

将来のお金の不安を軽減するためには、お金の増える力を高めることが重要です。
お金が増える複利の仕組みをわかりやすく解説します。
複利とは?利息が利息を生みお金が増える仕組み
複利とは、利息にさらに利息がつく仕組みです。
時間が長ければ長いほど効果が大きく、繰り返すことで利息が雪だるま式に増えるのが特徴です。
複利は「元本+利息」に利息がつく一方、単利は「元本のみ」に利息がつくため、複利と比較するとお金の増え方は小さくなります。
早く始めるほど有利!複利の効果を数字で解説
複利での資産運用は、早く始めるほど有利です。
100万円を年利5%で運用した場合の単利と複利のお金の増え方は、以下の通りです。
| 経過年数 | 単利 | 複利 |
| 1年後 | 105万円 | 105万円 |
| 5年後 | 125万円 | 127万円6,300円 |
| 10年後 | 150万円 | 162万円8,900円 |
| 20年後 | 200万円 | 265万円3,300円 |
10年・20年と運用期間が長くなるほど、複利効果が大きくなることがわかります。
若いうちから資産形成を始めることで、複利効果を最大化できるでしょう。
家庭でできる小学生向け金融教育4つの方法とおすすめ教材
子どもがお金に興味を持ち始めたら、金融教育を始めるのがおすすめです。
家庭でできる小学生向け金融教育の4つの方法と、親子で楽しく学べる金融教育教材も一緒に紹介します。
① お小遣い管理で自己管理スキルを身につけよう
お小遣い管理では、お金の使い道などを記録し可視化することで、自己管理能力を養うことができます。
必要なものと欲しいものを区別することやお金には限りがあることなど、自然に学べます。
お金を計画的に使う習慣は、将来の家計管理や生活設計にも役立つでしょう。
無駄遣いしたり、記録し忘れたり、失敗することもあります。
適切な金銭感覚を身につけるためには、失敗から学び改善することも大切です。
② ゲームや本の教材で楽しみながら学ぶ
ボードゲームや投資シミュレーションができるスマホアプリなど、ゲームでも楽しみながらお金の仕組み・経済の流れを学ぶことができます。
文字が苦手な子には、無理なく読み進められる漫画がおすすめです。
③ 金融庁が提供する教材や動画を活用する
金融庁では、小学生向けの金融教育に役立つ教材や動画が公開されています。
「うんこお金ドリル」では、子どもに人気のキャラクターとお金について楽しく学ぶことができます。
「くらしと金融」は、金融機関やお金の流れを紹介しているパンフレットです。
「お小遣いからまなぶお金の話」ではお金の基本知識や使い方などがクイズ形式で出題されているため、小学生でも理解しやすいでしょう。
「小学生のためのハッピー・マネー教室」は、お金の大切さや投資について学ぶ授業形式の動画です。
【参照:金融庁https://www.fsa.go.jp/・金融経済教育推進機構(J-FLEC)https://www.j-flec.go.jp/
金融庁・文響社「うんこお金ドリル」https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/unko/
金融庁「くらしと金融」https://www.fsa.go.jp/teach/kurashi/index.html
「小学生のためのハッピー・マネー教室」動画教材https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/attention/02/index.html
金融経済教育推進機構(J-FLEC)「金融を学べる教材」https://www.j-flec.go.jp/materials/】
④金融教育に特化した塾・スクールで実践的に学ぶ
子どもへの金融教育は、お金に興味を持ったタイミングで始めることが大切です。
しかし、金融教育を受けていない親御さんは、お金の知識が十分でないため、子どもに正しい知識を教えることが難しい場合もあります。
金融教育スクールMIRADASでは、ディスカッションや投資体験を通じて、小学生から経済とお金の本質を実践的に学ぶことができます。
学習塾の東進ゼミナールが運営する金融教育スクールのため、安心して検討できるでしょう。
まとめ:小学生からの金融教育で金融リテラシーを身につけよう!
小学生から正しい金融知識を身につけることは、将来の安心や豊かな人生につながります。
金融教育は、キャッシュレス化や年金不安など社会の変化とともに必要性が増しており、金融庁においても生きる力として重視されている学びです。
金融教育は、子どもがお金に興味をもったタイミングでお小遣い管理や本・ゲームなどの教材を活用して家庭でも始められます。
しかし、学校の授業で金融教育を受けていないため正しい知識を伝えられるか不安、という親御さんもいるでしょう。
金融塾では、体験型のマネー教育プログラムによりお金と経済について実践的に学ぶことができます。
将来のために子どもの金融リテラシーを高めたい親御さんは、MIRADASをチェックしてみてはいかがでしょうか。