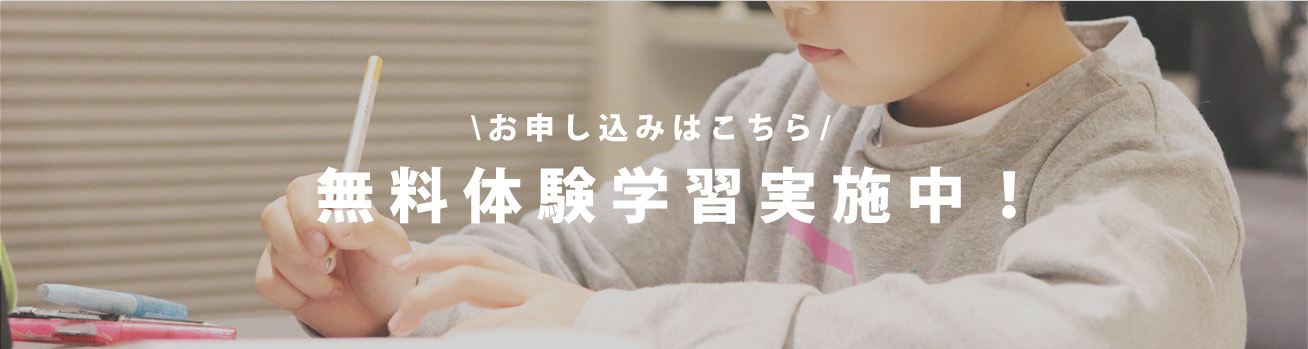「うちの子、ちゃんと考えて行動できてるかな?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
最近の教育現場では、「論理的思考力」がますます重要視されています。
ただし、これは難しい問題を解く力ではありません。日常の中で「なぜ?」「どうして?」を考えるクセをつけるだけでも、十分に鍛えることができます。
この記事では小学生の論理的思考力とは何か、その必要性、そして家庭でできる具体的なトレーニング方法を紹介します。ドリル・ゲーム・読書など、楽しみながら取り組める内容を中心にまとめました。
この記事のコンテンツ
論理的思考力とは?小学生に必要な理由

論理的思考力とは、「なぜそうなるのか」「どうしてそう考えたのか」を、順序立てて説明する力です。
たとえば、「雨が降っているから傘を持っていく」という判断にも、事実→理由→行動という筋道があります。こうした思考の流れを理解し、言語化する力が論理的思考力です。
この力は、国語の読解や算数の文章題だけでなく、友達との会話や授業での発表、将来の仕事など、さまざまな場面で必要とされます。
また、小学校では「主体的・対話的で深い学び」が重視されるようになり、「なぜそう思うのか」を説明する機会が増えています。論理的に考え、自分の言葉で伝える力は、今後ますます求められるスキルです。
論理的思考力の意味と例
論理的思考は、特別なことではありません。
たとえば「今日は体育があるから動きやすい服にした」という判断も、立派な論理的思考です。
大事なのは「理由を持って選ぶ」ことです。
自分の考えを、言葉で伝える機会を増やすことで、この力は自然と身につきます。
なぜ今、子どもに論理的思考力が求められるのか
情報があふれる時代では、「正解を覚える力」よりも「考えて選ぶ力」が重視されています。
AIの登場や働き方の多様化により、自分の意見を持ち、理由を伝える力が、これからの社会では必要不可欠です。
また、教育現場でも記述式の問題が増え「どうしてそう考えたか」を問う問いが主流になりつつあります。
論理的に考え、言葉にする力は、将来の受験や就職、対人関係でも大きな武器になるでしょう。
幼児期からの積み重ねが重要な理由
論理的思考力は、一朝一夕では身につきません。
「どうして?」「なんで?」といった疑問を、日々一緒に考える積み重ねが大切です。
「なぜ片づけが必要なの?」「どうして寝る時間なの?」
そんな問いに、正解を教えるのではなく、子どもと一緒に考える姿勢こそが、思考の土台を育てます。
たとえば、おもちゃを片づけるときに「どこに置いたらまた遊びやすいかな?」と問いかけたり「今日の予定はどうしたい?」と選ばせたりするだけでも効果的です。
大人が先回りして指示を出すのではなく「自分で考える場面」を意識してつくることで、子どもの思考は少しずつ深まっていきます。
ドリルで身につく!論理的思考を鍛える練習法

ドリルは、考える力をトレーニングするのにぴったりの教材です。
特に選択式の問題は、「なぜそれを選ぶのか?」を自分で考えるプロセスが含まれており、論理的な判断力が自然と育ちます。
選択式問題が論理力を育てる理由
選択式の問題では、単に答えを選ぶだけでなく、複数の選択肢を比べながら「どれが一番ふさわしいか?」を考える必要があります。
この「比較・分析・判断」のプロセスが、論理的思考力を育てるのにぴったりです。
「なぜこれを選んだのか」「どうして他を選ばなかったのか」と自分の頭で理由を整理する力が、選択式の問題を通して少しずつ養われていきます。
市販のおすすめドリル3選
市販のドリルにも、論理的思考力を伸ばせるものがあります。
・ロジカルキッズワーク(学研):図解や選択問題で思考を整理する力を育成
・5分で論理的思考力ドリル(学研×ソニー):短時間で集中して取り組める構成
・天才脳ドリル 仮説思考(受験研究社):仮説と検証のトレーニングに特化
いずれも家庭で無理なく取り組めるので、まずは子どものレベルに合ったものから始めてみましょう。
それぞれのドリルには独自の特徴があります。たとえばロジカルキッズワークは低学年でも取り組みやすく、図解を通して“目で見て考える”力を育てられます。
一方、5分ドリルはすきま時間に取り組めるため継続しやすく「考える習慣づけ」に最適です。
天才脳ドリルは難易度が高めですが、仮説と検証をくり返す構成なので、中学受験などを見据えた家庭にも人気です。
金融塾「MIRADAS」で選択力を伸ばす
小学生のうちから「お金」と「経済」を実感しながら学べるのが、ファイナンシャルスクール「MIRADAS(ミラダス)」です。ミラダスは小学生〜高校生を中心に、バーチャル投資シミュレーションやディスカッションを通して、知識を覚えるだけでなく判断力やファイナンシャルIQを育てる体験型プログラムを提供しています。
学び方の核は「バーチャル投資×対話」です。実際の企業や経済の動きを題材に、投資のシミュレーションで仮説を立てて検証し、意見交換や発表で自分の考えを言語化します。これにより、情報収集→分析→判断→発信の流れをくり返し、考えて選ぶ力を実践的に鍛えられます。
授業は少人数制で、曜日や時間も柔軟に選べるため、習い事と両立しやすいのも安心です。まずは無料体験で雰囲気を確かめることもできます。はじめての子でも、レベルに合わせたカリキュラムで基礎から無理なく学べます。
ミラダスの学びは、単なる知識の暗記ではなく、企業リサーチや市場理解を通じて「自分で考え、行動する」力を育てることが目的です。将来の選択肢を広げたい、日常のニュースを自分ごととして理解したい、という家庭に向いた実践型の金融教育です。
遊びながら学ぶ!思考力を刺激するゲーム集
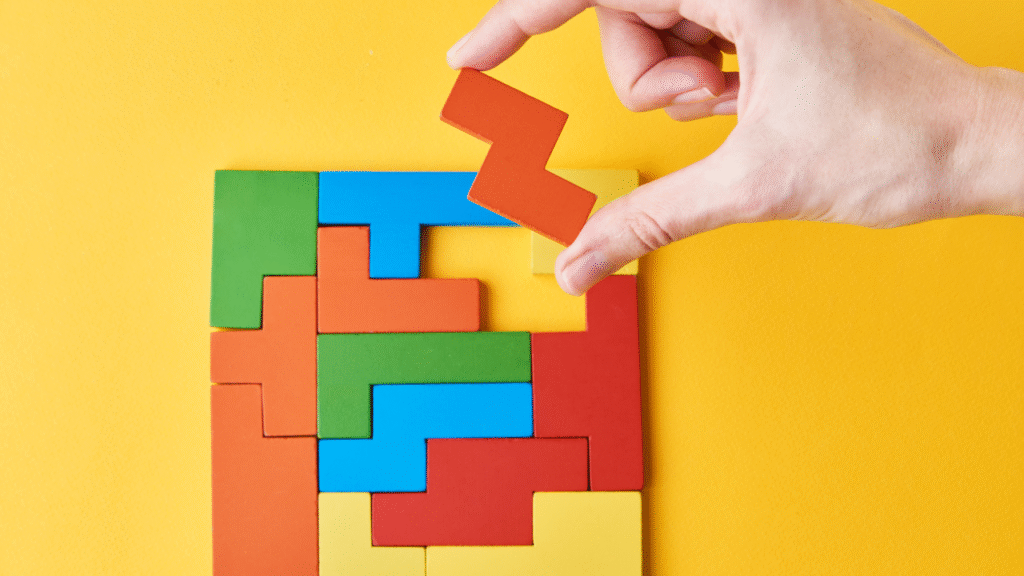
論理的思考力は、遊びの中でも楽しく鍛えることができます。
とくにボードゲームや知育アプリは、遊びながら考える力を自然に育てられるのが魅力です。
ボードゲーム:ナンジャモンジャ・ウボンゴなど
『ナンジャモンジャ』では、キャラクターに名前をつけ、それを覚えて再登場時に呼ぶルールになっています。記憶力だけでなく「どうすれば覚えやすいか」「この名前はどんな特徴か」と考えることが思考力につながります。
『ウボンゴ』は、図形のピースを組み合わせて正解を導くパズルゲーム。
制限時間内で答えを見つけるためには、順序や空間の整理を論理的に考える必要があります。
デジタルゲーム:Think!Think!など
スマホやタブレットで使える知育アプリもおすすめです。
とくに『Think!Think!』は、空間認識や図形の組み合わせ、仮説思考を楽しく学べる設計で、1回3分で取り組めるのが魅力です。
すきま時間に気軽に続けられるため、家庭でも取り入れやすい学習ツールです。
自作クイズやしりとりで考える力を引き出す
特別な教材がなくても、家庭でできる工夫はたくさんあります。
「3つのヒントでモノを当てるクイズ」や「しりとりで特定のルールを加える」など、自分たちでルールを考える遊びは、柔軟な発想と論理的なルールづくりの練習になります。
ちょっとした工夫で、日常が学びの場になります。
たとえば「食べ物で赤いものだけしりとり」や「ヒント3つで何かを当てるゲーム」など、ちょっとした制限を加えるだけで論理的に考える遊びになります。
その場でルールをつくったり変更したりする柔軟さも、子どもの創造力と論理力を刺激します。
読書で育つ論理的思考!年齢別おすすめ本

本を読むことは、登場人物の気持ちや展開を想像する力、因果関係を理解する力を育てます。
論理的思考を無理なく伸ばすのにぴったりな方法です。
論理的思考力を育てるには、ドリルやゲーム以外にも、日常の中にある「小さな選択の積み重ね」がとても大切です。
たとえば、服を選ぶときに「どっちがいい?」と聞いてみると、「今日は体育があるから動きやすい服にする」など、理由をもとに判断する力が育ちます。
また「ごはんとお風呂、どっちを先にする?」といった問いでも「今はおなかが空いているから先にごはんにする」と自分で考えるきっかけになります。
こうした日常の選択肢を与えるだけでも、子どもは「理由をもって決める」練習ができます。
さらに「なぜそうしたの?」とやさしく聞いてあげることで、自分の考えを言葉にする力も自然と伸びていきます。
読書や学習に入る前段階として、こうした“自分で考えて選ぶ”体験を積み重ねることが、論理的思考の土台になるのです。
低学年向け:絵本や短編集で考える習慣を
短くてわかりやすい物語の中にも「なぜこうなったのか?」「もし自分だったら?」と考える要素が詰まっています。
『14ひきのシリーズ』や『ぐりとぐら』など、親しみやすい絵本からスタートすると、抵抗なく読書習慣が身につきます。
選んだ理由や登場人物の気持ちを親子で話し合うことで、読んだ内容を“自分の考え”として定着させることができます。
「なんでこうしたと思う?」「このあとどうなると思う?」など問いかけながら読むと、論理の流れを意識できるようになります。
中・高学年向け:読解・推論型の読み物
この時期には、登場人物の心情や物語の構造を読み解く力が求められます。
『かいけつゾロリ』『名探偵シリーズ』など、物語の中に“考える要素”が含まれている作品がおすすめです。
登場人物の行動や背景にある動機を考えることで、文章を深く読み取る力が育ちます。
また、探偵ものやクイズ形式のストーリーなどは、「手がかりから推理する」経験を楽しみながら積めるため、論理的に考えるクセづけに効果的です。
親子で一緒に読むならこの1冊
親子で一緒に読むなら、『考える練習をしよう(PHP研究所)』のような「思考そのもの」をテーマにした本もおすすめです。感想を共有することで、自然と論理的な会話のキャッチボールが生まれます。
読んだ後に「自分だったらどうする?」「同じ場面で違う選択肢はある?」と親子で意見を交わすことで、会話そのものが思考のトレーニングになります。大人にとっても、新たな視点や気づきを得られる機会になります。
論理的思考力を家庭で無理なく鍛えるコツ

毎日の生活の中に、「考えるきっかけ」を取り入れることが大切です。
以下に、親子で取り組みやすい工夫をいくつか紹介します。どれも特別な準備は不要で、すぐに日常に取り入れられるものばかりです。無理なく、楽しく続けることが、思考の習慣づけにつながります。
日常会話に「なぜ?」を取り入れる
「なぜそうしたの?」「どうしてそう思ったの?」と問いかけるだけで、思考の習慣が育ちます。
正解を求めるのではなく、「自分の考えを言葉にする機会」を意識しましょう。
答えのない問いで柔軟な思考を育てる
「もし1つだけ願いがかなうなら?」「100円あったら何に使う?」など、正解のない問いを投げかけることで、子どもは自由に思考を広げることができます。
正解のない問いは、「どう答えるか」より「なぜそう考えたか」に注目できます。
「友達が2人いたら、どちらと遠足に行く?」「未来の自分に手紙を書くなら何を書く?」など、遊び感覚で取り入れることができます。
続けるコツは「楽しい」と「ちょうどよさ」
むずかしすぎる内容では続きません。子どものレベルや関心に合わせて、「できた!」「おもしろい!」という感覚を積み重ねていくことが大切です。
「少し考えればわかる」「頑張れば解ける」くらいの難易度が最適です。
また、達成感を味わえるように、終わったあとに褒めたり、スタンプを押したりするごほうびも効果的です。
続けること自体が目的ではなく、「考えるのって面白い」と感じる経験が、将来の思考力の土台になります。
まとめ:楽しみながら思考力を伸ばそう
論理的思考力は、「日常の中でちょっと考える習慣」から育ちます。ドリルや読書、ゲームなど、子どもが楽しみながら取り組める方法を選べば、無理なく続けることができます。
大切なのは、「正解を出すこと」ではなく、「なぜそう思ったのか」を考え、言葉にすること。
親子の会話や日常の選択を通じて、その練習はいつでも、どこでもできます。
さらに、「実践的に考える力を育てたい」と感じたら、選択と対話を軸にした学びを体験できるファイナンシャルスクール「MIRADAS(ミラダス)」をのぞいてみてください。
経済や投資といった身近ではないテーマを通じて、「考えて選ぶ」力を、ゲームのように楽しく鍛えることができます。
家庭での工夫に加えて、こうした場を上手に活用することで、子どもの考える力は、もっと大きく育っていきます。