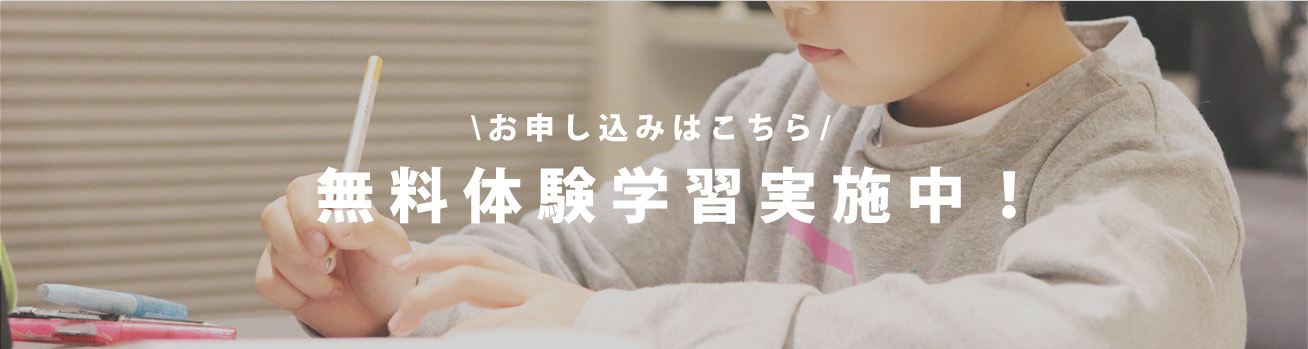子どもに正しいお金の使い方や考え方を伝えることは、将来の自立や安心した暮らしにつながる大切な教育のひとつです。学校教育では十分に扱われないテーマだからこそ、家庭での教え方が子どもの金融リテラシーを大きく左右します。
どのように教育すればいいのかと、迷っている親御さんも多いのではないでしょうか?この記事では、子どもの成長段階に応じて実践できるお金の教育方法をわかりやすく紹介します。安心して活用できる教材や公的機関の情報もまとめました。
この記事のコンテンツ
子どもにお金の教育を行うメリットとは?

お金は自立して生活するうえでは、必須といえます。子どものときから、お金の教育を行うことで、お金の知識を得ることができ、資産形成のやり方も身につくでしょう。
金銭感覚が身につく
お金の教育によって、子どもは金銭感覚が身につきます。いくら使えば無駄遣いしないのか理解できるので、限られたお金をどう使えばいいのかわかります。例えば、お小遣い帳をつけたり、予算を決めて買い物することで、お金を使うときの適切な金額はいくらかわかるでしょう。
必要なものだけ買うのが良いとわかり、無駄遣いを減らすので、大人になってからの生活設計や金銭管理にも役立ちます。
資産形成が重要だと理解できる
子どもの頃から、貯めて増やすという考え方を学ぶと、将来にわたって資産形成が重要だと理解できます。お金は使うだけではなく、収入以外の方法でも増やすこともできると学べるでしょう。そして、大きくお金を増やすには、資産形成が有効だとわかります。
貯金箱を使い少額から積み立てたり、投資や利息について説明を聞いたりすると、資産形成の概念が理解できます。社会人になっても、計画的な貯蓄や投資が行えるようになり、経済的な安定を得ることが可能です。
税金や社会保障の知識を得られる
税金や社会保障は、大人になると避けて通ることはできません。しかし、学校教育だけでは、十分な知識を得られない場合が多いです。子どものときに知識を身につければ、税金や社会保障がどのように使われており、大人になるといくら支払うのかわかります。
家庭内で、消費税の割合や使われ方、医療保障や年金を支える仕組みや使われ方などを教えておきましょう。税金や社会保障を正しく理解できれば、大人になっても、税金や保障を正しく捉えて、責任感や公共意識が育まれます。
家庭で子どもにお金の教育を行うときのポイント

子どもはお金に触れる機会は少なく、社会の仕組みも知らないために、お金がどんな役割をするのか理解しにくいです。難しいことを言っても理解できないので、身近な事例や簡単なことから教えていきましょう。
対価に対してお金は得られるということ
子どもはお小遣いとしてお金をもらうので、大人のように対価を払ってお金を得るということがわかりません。そこで、対価で得られるということも、家庭内で実践して体感してわかるようにしてあげましょう。
例えば、家の手伝いをした対価としてお金を渡す、図画工作のような制作物やおやつを作り、その品物に対してお金をあげるということをしてみます。なにか価値のあることをするとお金が得られると分かれば、労働感やお金の価値観を育むきっかけとなるでしょう。
お金の貯め方や使い方を教える
お金は使うだけではなく、貯めることも覚えないといけません。計画的に貯めることが重要だと教えてあげましょう。子どもに銀行口座を開設してあげて貯金させたり、家の貯金箱で貯めたりできます。欲しいものがあれば、目標金額を設定して貯めるようにさせてあげましょう。
貯めたお金をどのように使うか考えれば、優先順位を考えるクセが付き、浪費を防ぐことも考えられます。
学校の友達同士のお金の貸し借りは危険
子どもには、個人同士での貸し借りは金銭トラブルになるということも教えてあげましょう。そして、金銭トラブルはやがて相手との決別にも繋がり、友達や知人を失う結果となると教えます。
ただし、言葉で教えても子どもはなぜトラブルになるかイメージしにくいです。そこで、子どもの周りの身近な品物を例えにして教えます。例えば、ゲーム機や自転車などです。友達に貸して返してくれないとどうなるか、子どもに教えるとイメージできるでしょう。それがひいては、お金も同じだとわかるようになります。
お金に関する些細なことでも相談させる
子どもはときには、言うのをためらうこともあります。そのため、お金に関しても小さなことでも相談させましょう。これを買ってもいい?どうやって貯めたらいい?などを聞いて理解することで、子どもはお金の判断力や意思決定力を身に着けます。
些細なことでも相談させるには、親は家庭内の問題を子どもに隠さないようにすることが必要です。子どもに悪影響があるからと、家庭内トラブルを隠そうとする、できるだけ大事にならないようにするというのでは、子どもは気軽に親に相談できません。
実際の教育の方法

子どもは難しいことを言っても理解できません。家庭でお金の教育を行うときは、わかりやすい言葉や身近な出来事で教えてあげましょう。
小遣い管理で家計簿をつけさせる
お小遣いは、子どもが得られる収入です。このお小遣いの使い道を家計簿に記録させ、お金の管理をさせてみましょう。
毎月決まった金額を渡して、その中でやりくりさせると、金銭感覚がわかり自然と計画性を学びます。最近は家計簿アプリや子ども向けの家計簿も登場しており、小さいときでもお金の記録をつけやすくなっています。
買い物で金銭感覚を養わせる
買い物をお金の使い方を学べる実践的な場所です。予算を決めて買い物をさせると、限られたお金の中で何を優先すればいいのかとわかるでしょう。そして、お金は有限ではなく、限られた中で使う必要があると理解できます。
さらに、肉や魚、野菜と1つとっても、店で値段が違い、量によっても違ってくると実感できます。親子でいくつかの店を回って、それぞれの店の品物の価格を見ていくと、如何に安い品を買うかというのも考えるようになるでしょう。そして、コストパフォーマンスを意識するようになります。
親の仕事からお金について教える
親の得ている給料も、子どもがお金について考える良い材料です。父母が働いているから家庭ではお金を使うことができ、そのお金で生活が成り立っていると教えてあげましょう。子どもへのお小遣いも、給与があるからこそ与えられると知らせます。
そして、得られた給与は何に使うかも教えましょう。生活費や家賃に使用し、一部は貯蓄して将来に備えていると伝えます。働いているからこそ、毎日ご飯を食べられると教えれば、働くことの大切さを実感できるでしょう。
実際に資産運用させてみるのは何歳から
お金について学ぶときは、資産運用も良い方法です。成人するのを待たなくとも、工夫すると子どものときから資産運用について学べます。例えば、簡単な数字で利息のことを教えれば、お金は資産運用で増やすこともできるとわかります。
中学生以降になったら、親と一緒に少額から株や資産運用をしてみるのも良いでしょう。大切なのは、リスクとリターンがあるということです。資産運用はお金を増やすばかりではなく、失うリスクもあると教えてあげてください。
年齢別の教育方法の例

小さい頃から急に投資させてもわかりにくく、子どもも興味を示すことが少ないです。年齢に応じた、わかりやすい方法でお金の教育をしましょう。
小学生卒業まで
お金に触れる機会の少ない小学生までの時期は、お金の基本について教えてあげます。お小遣いを通じて、お金には限りがあると実感できるようにしてあげましょう。欲しいおもちゃを買うために、毎月貯金させると貯めるということもわかります。
高学年になったときは、家計簿をつけたり買い物で品物の値段を比べたりと、より実践的な内容に移します。値段を比べて、選ぶんでより安い製品や性能の優れた製品を選ぶという体験をさせてあげましょう。
中学生から高校生
中学生以上の子どもには、より現実的なお金の使い方を教えます。昼飯や定期代、交遊費などと使うお金が増えるため、毎月の小遣いやアルバイトの収入を、何にいくら使うか考えさせましょう。
高校生であれば、少額で資産運用をさせても良いでしょう。このときに、親がサポートして銘柄の選び方や損失での気持ちの構え方を伝えます。キャッシュレス決済を使うようにさせて、利便性やリスクを教えるのも良いです。
お金の教育に使える本やアプリなどの教材

ここからは、子どもにわかりやすく教えられるお金の教育に使える本やアプリを紹介します。
金融塾「MIRADAS」
小学生・中学生・高校生を対象にした金融塾であり、仮想通貨を使って経済とお金の本質について学べます。バーチャル投資を行うので、実際の投資に近い体験ができ、お金の本質がわかります。
学校では教えてくれない、家計や税金についても学ぶことが可能です。子供の頃から学ぶと、将来の税金について理解できます。そして世界情勢や経済のニュースを見て、株価がどのように動くかも知ることができ、ニュースの捉え方が変わります。
学ぶ曜日や時間は自由に選べるため、時間の都合を合わせやすく、放課後や休日に学ぶことが可能です。
未成年が資産運用体験できる「株たす」
実際の株価データを使用し、株式投資を体験できる、投資運用のシミュレーションアプリです。数千種類もの銘柄に対応しているので、さまざまな角度から銘柄を選んで株式投資を体験できます。ミニ株にも対応しており、1株からの投資体験も可能です。
実際に株式投資を行うと、証券会社の口座を開設し、投資資金を用意しないといけません。子供時代に多額の資金を用意するのはほとんど不可能であり、気軽に投資は行えません。
しかし、株たすを使うとアプリによってスマートフォンで、気軽にシミュレーションによる株式投資体験を行えます。実際の運用とは違い、損失が発生してもお金が減ることがないので、子どもでも安心して投資シミュレーションを行えます。
金融教育本の「10歳から知っておきたいお金の心得」
小学生にわかりやすいように、お金について1つずつ教えてくれる本です。書籍の構成は、物の価値・未来のお金・銀行・税金・投資や保障となっています。大人として生活するうえでお金について必要な内容を網羅します。
書籍内の漢字にはすべてふりがながついており、イラストも入っているので、子どもでも飽きにくいです。そのため、親子で一緒に本を見ていきお金について学ぶこともできます。
書籍内では、通貨の変わりに使われていたものや、ユニークな税金についても紹介されており、飽きずにお金について学べる工夫がされています。お小遣いでお金を学ぶ方法も巻末についており、より実践的に学ぶこともできます。
お金の教育は「MIRADAS」がおすすめ!

大人になると、給料や税金とお金については避けることができません。子どもはお金に触れる機会が少ないですが、早いうちに学んでおけば貯めたり工夫してお金を使う癖がつきます。投資についても学ぶと、将来役に立つでしょう。
お金について学べる教材はいくつもありますが、中でもMIRADASがおすすめです。お金の基本から税金や株価など具体的な内容まで学べます。わからないことがあれば、講師に聞くこともできるので、教えてもらったけどわからないということを防げます。