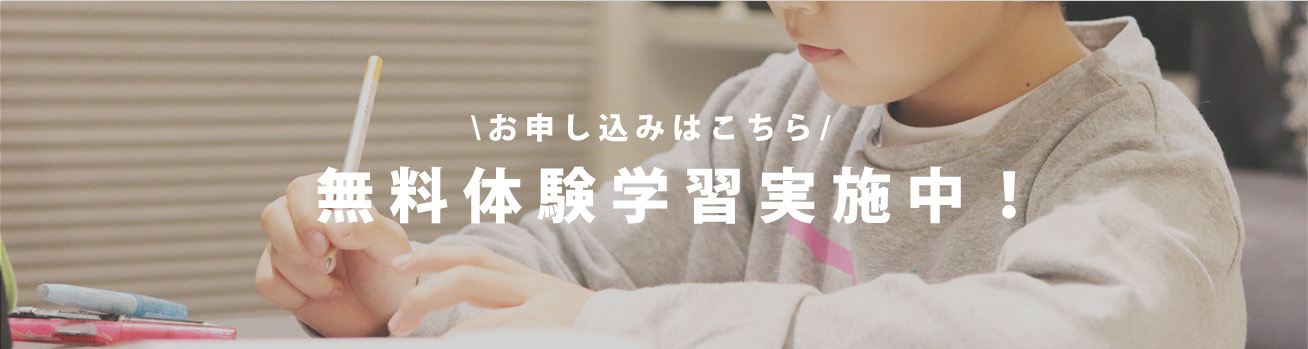子どもにとって「お金」はまだ身近でありながら、どのように扱えばいいのか、分かりにくいものです。だからこそ、中学生のうちに家庭で少しずつ「経済やお金の習慣」を身につけておくことが大切です。難しい勉強をする必要はありません。お小遣いの使い方を一緒に考えたり、買い物のときに価格を比べてみたり、日常の会話の中で自然に学べる工夫がたくさんあります。今回の記事では、保護者の方が無理なく取り入れられる「家庭でできる経済教育」のヒントをご紹介します。
この記事のコンテンツ
なぜ中学生のうちに経済感覚を身につけるべきなのか

中学生は、自分で考えて行動する力が少しずつ育ち始める時期です。部活動や友人関係が広がり、お小遣いや買い物を通じて「お金を使う機会」も増えていきます。この時期に、経済感覚を身につけておくことで、計画的にお金を管理する習慣が自然と身につくでしょう。将来の自立にもつながります。
逆に、大人になってから急に「貯金」「節約」「投資」といったテーマに直面すると、基礎がない分だけ、戸惑いや失敗をしやすくなってしまいます。家庭の中で無理なく学ぶことが、子どもにとっての一生の財産になるのです。
早期に経済を学ぶことで将来の選択肢が広がる
経済やお金のことを早いうちから学んでおくと、子どもが大きくなったときに選べる道がグッと広がります。たとえば、高校や大学での進路を考えるときに「学費や奨学金」を理解しているかどうかで、選択肢は変わるでしょう。
将来の夢に向けて、必要なお金をどのように準備すればいいかを、考える力にもつながります。社会に出てからも「お金の知識」があることで、無駄な出費を減らして、自分の人生をより自由にデザインできます。家庭での小さな学びが、子どもの未来を広げる大きなきっかけになるのです。
【中学生目線でまずは考える】中学生が理解すべきお金の基本

中学生になると、お小遣いやスマホ決済、部活動や趣味にかかる費用など、「お金」を自分で使う場面が少しずつ増えてきます。しかし、なんとなく使っているだけでは、本当に大切なことは見えてきません。まずは「お金とは何か」「なぜ管理する必要があるのか」といった基本を理解することが、これからの生活や将来の選択肢を広げる第一歩になります。ここでは、中学生の目線でわかりやすく、お金の基本を整理してみましょう。
そもそもお金の価値とは
私たちが毎日使っているお金は、ただの紙や数字に見えますが、本当の価値は「みんなが信用していること」にあります。100円玉そのものの金属には大きな価値はありませんが、「100円でお菓子が買える」と社会全体が認めているからこそ、安心して使えるのです。
お金があることで、物々交換をせずにスムーズに買い物ができます。将来のために貯金することも可能になります。つまり、お金は生活を支える「大切なモノ」です。中学生から「お金の価値」を正しく理解しておくことが、これからの選択肢を広げる第一歩になるのです。
お小遣い管理の大切さ
お小遣いは、ただ好きなものを買うためのお金ではなく、「自分でお金をどのように使うか」を学ぶ大切なチャンスです。欲しいものをすぐに買ってしまうと、必要なときにお金が足りなくなって困ることがあります。逆に計画的に使えば、本当に欲しいものを買うために貯めたり、友だちとのイベントに備えたりすることができます。
限られたお小遣いをやりくりすることは、大人になってからの家計管理や、お金の使い方の練習にもつながるのです。お小遣い帳をつけたり、月の予算を決めたりする工夫を通して、「お金を大切に扱う力」を少しずつ身につけることが大切です。
中学生を持つ家庭で実践できる経済教育の方法

中学生の時期は、お金に対する理解を深める大切なタイミングになります。家庭でのちょっとした工夫や会話が、将来の経済感覚やお金の使い方に大きく影響します。学校では教わりにくい「生活に直結する経済教育」を、家庭の中で自然に取り入れることができれば、子どもは楽しみながら学べるでしょう。自分で考えて行動する力が養われます。ここでは、中学生を持つご家庭で無理なく実践できる経済教育の方法をご紹介します。
お小遣い帳やアプリで収支を管理する
お小遣い帳や家計管理アプリを使って、自分のお金の出入りを記録することは、経済感覚を身につける第一歩です。毎日の支出や収入を可視化することで、「何にいくら使ったか」「どこで節約できるか」が自然に理解できます。中学生でも簡単に始められる方法なので、ちょっとしたゲーム感覚で、楽しみながらお金の管理力も育てられます。
家族で経済を意識した買い物体験を行う(値段の比較・予算管理など)
家族で一緒に買い物に出かけて、値段の比較や予算内での買い物を体験することは、中学生にとって貴重な経済教育の場になるでしょう。たとえば、同じ商品でも、スーパーごとに価格が違うことを比べたり、予算を決めてその中でやりくりしたりすることで、自然と「お金の使い方を考える力」が身につきます。楽しみながら学べる体験型の学習として、家庭で取り入れやすい方法です。
親子で経済ニュースや記事を一緒に読む習慣をつける
親子で経済ニュースや記事を一緒に読む習慣を持つことは、中学生にとって、お金や社会の流れを理解するきっかけになります。ニュースの内容について話し合うことで、「なぜ物価が上がるのか」「税金や貯金がどのように影響するのか」といった実生活に直結する知識が身につくでしょう。難しい内容も親子で一緒に考えることで、自然と経済感覚や判断力が鍛えられます。
外部学習で中学生の選択肢を広げるのも大切

家庭での学びだけでなく、外部の学習や体験を通じて中学生の視野を広げることも、経済教育には欠かせません。たとえば、金融機関の見学やワークショップ、職業体験、マネー塾などに参加することで、お金の流れや社会の仕組みを実感として学べます。家庭では伝えきれないリアルな経験は、子どもの将来や選択肢を考える力を育む、大きな助けになります。
マネー塾や外部学習で得られるメリット
外部学習の参加によって、実践的に経済を学べるのが特徴です。特にマネー塾は、お小遣いの管理や予算の立て方、貯蓄や簡単な投資の仕組みまで、体験型のカリキュラムを通じて、具体的に学習できます。同年代の仲間と意見を交換したり、講師からリアルな事例を聞いたりすることで、経済への関心が自然に高まります。家庭での学びを補完する、実践的な経済教育の場としてメリットがあるのです。
外部学習で学べる経済テーマについて
外部学習では、中学生でも理解しやすい身近なテーマから、少し高度な経済の仕組みまで幅広く学べます。たとえば、「お金の流れ」や「利息・投資の基本」を知ったり、買い物体験で「価格の比較」「予算管理」の重要性を実感したりできます。収入と支出のバランスや、経営の考え方など、実社会に直結する経済テーマも多いです。
経済感覚を養うための家庭学習と外部学習のバランス

中学生に経済教育を行う際には、家庭での学びと外部での体験をバランスよく取り入れることが大切です。日常生活の中でのお小遣いや買い物体験、ニュースや記事を通した社会の動きの理解など、身近な場面と結びつけてください。学んだ知識がリアルに感じられます。
また、子どもの興味や性格に合わせた学び方を見極めることで、とっつきにくい経済分野の苦手意識を生み出しません。ゲーム感覚で学ぶのが向いている子もいれば、ニュースを一緒に読む方が理解しやすい子もいます。まずは、子どもの得手不得手を理解してみましょう。
学んだ内容を日常生活やニュースに結びつける
学んだ内容をニュースや日常の出来事と結びつけることで、学習が現実生活に直結していることを実感させることができます。家庭学習と外部学習をうまく組み合わせることで、中学生は単なる知識の習得にとどまらず、それ以上の相乗効果が期待できるでしょう。
子どもの興味・性格に合った学習スタイルを見極める
家庭では、子どもの様子をよく観察して、何に夢中になっているか、どのように学ぶと楽しそうかを把握してみてください。大切なのは、正しいやり方にこだわりすぎず、子どもが楽しみながら学べる環境を整えることです。
興味・性格に合わせた学習スタイルを見つけることで、学ぶ力だけでなく、自分で考えて、選択する力も育まれます。将来にわたって学び続ける力の土台を作るために、子どもの個性に寄り添った学びを取り入れてみましょう。
中学生の子どもに経済に興味を持たせるコツ

「お金のことは難しそう」と感じる中学生も少なくありません。しかし、身近なお小遣いや買い物、ニュースで見かける経済の話から学ぶことで、少しずつ興味が持てます。大切なのは、難しい理論を押し付けるのではなく、子ども自身が「知りたい」と思える体験や工夫を取り入れることです。ここでは、中学生の子どもが楽しく、無理なく経済に関心を持てるようにするコツを紹介します。
小さな成功体験を積み重ねる
経済の勉強は、難しいことから始めなくても、全く問題ありません。まずは、身近なお金のことから始めて、小さな成功を積み重ねることが大切です。たとえば、「お小遣いを使うときに計画を立てて守れた」「少しずつ貯金ができた」そのような経験が、子どもの自信になります。小さな成功を積むと、「経済って面白いかも」と思えるようになり、自然ともっと知りたい気持ちがわいてきます。
経済ニュースや市場の動きを意識させる
子どもが身近で興味の持ちやすいテーマを選びましょう。一緒にニュースを見て話し合う時間を作ることが重要です。たとえば、コロナ禍の影響や身近な経済活動の変化など、子どもが当事者意識を持てる内容から始めると、関心が深まります。また、ニュースの「事実」だけでなく「なぜそうなったのか」という理由や背景を、考えるように促してください。論理的思考力や理解力が伸びます。保護者の方が「なぜだと思う?」と質問して、子ども自身に考えさせる対話が効果的です。
さまざまな立場からの意見や見方があることを伝えて、多角的に物事を見る力を養うことも大切です。経済対策の賛否や社会影響を、違う視点から話し合うことで、考える楽しさと興味が広がります。子どもが、社会や経済の動きに自然と関心を持ち、自分事として意識できるように導いていくことがポイントです。
無料オンライン学習・ゲーム感覚の経済学習ツールを活用する
無料のオンライン学習やゲーム感覚で経済を学べるツールは、子どもの金融リテラシー向上に、とても効果的です。ゲーム感覚でクイズに答えながらお金の知識を学べるアプリや、仮想空間で働いてお金の使い方を体験できるツールもあります。
また、子ども向けの仮想銀行アプリ「ハロまね」は、おこづかい帳や預金、金利の計算など実践的なお金の管理を疑似体験できる無料ツールです。このような無料アプリやゲームは、楽しみながら自然にお金の基本や経済の仕組みを理解できます。親子でのコミュニケーションや、教育の補助としても活用しやすいのが特徴です。
中学生向けのマネー塾を試してみる
お金のことは、学校の授業だけではなかなか学べません。そこでおすすめなのが、マネー塾MIRADASをはじめとした中学生向けのマネー塾です。ここでは、貯金やお小遣いの管理、買い物の計画、ニュースで見かける経済の仕組みなどを、ゲーム感覚や体験を通して学べます。
マネー塾を体験してみると、「お金ってどのように使うと得なのか」「どうやって計画的に貯めるのか」が、楽しみながら理解できるようになります。小さな成功体験を積むことで、子どもの自信にもつながるでしょう。家族や友だちに、学んだ内容を教えたくなることもあります。
このような中学生向けマネー塾では、体験コースや無料講座から、始めてみるのもおすすめです。自分に合った学び方を見つけるきっかけになり、将来の生活に役立つ経済感覚を、楽しく身につけられます。
お金や経済ニュースに興味があるならマネー塾MIRADASがおすすめ

今回の記事に触れたマネー塾MIRADASは、中学生が将来に役立つ金融や、経済の知識を身につけることができる特別なマネー塾です。授業では、家計管理や資産形成、景気や物価の変動など、日常生活に密接したテーマを分かりやすい形で学びます。現代社会で中学生にも必要となる、実践力や判断力を養う内容が盛り込まれているのが特長です。
自分のおこづかいや家計管理をシミュレーションできるだけでなく、チームで話し合うことで、社会とお金の関係を主体的に考えられます。これからの進路や生活設計への意識向上にも役立つでしょう。社会が複雑になる中で、早い段階から金融リテラシーを高めることは、将来トラブルに巻き込まれない力にもなります。マネー塾MIRADASは、これからの時代を生き抜くための基礎をしっかり学べる場として、多くの中学生におすすめできる学びの場です。