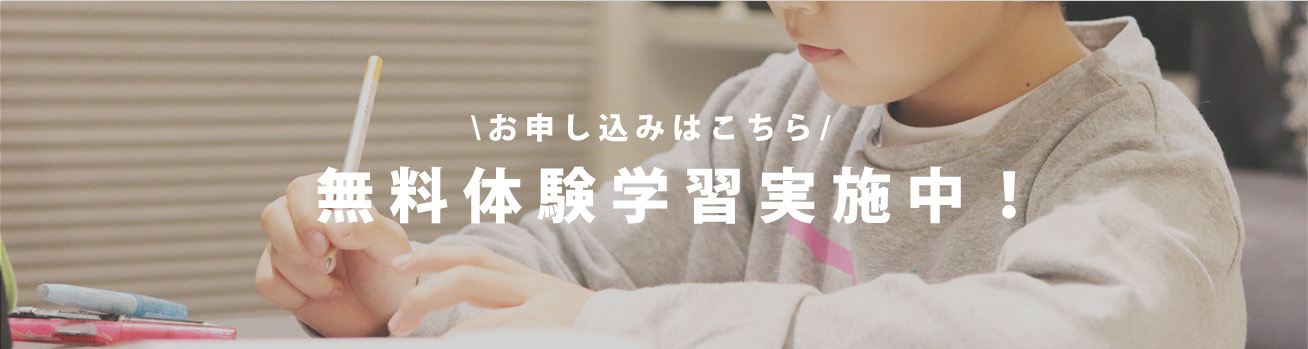小学生のうちから正しいお金の使い方を教えることは、子どもの将来にとって重要です。
しかし、共働きで忙しくて、お金の教育に時間を割けないと悩む親御さんも少なくありません。
共働き家庭でも小学生にお金の使い方を教えることは十分に可能です。
本記事では、お小遣い制度や買い物体験など、家庭でできる金融教育の方法を解説します。
さらに、公的機関が提供する教材の活用法や専門スクールについても紹介します。
この記事のコンテンツ
小学生のうちからお金の使い方教育・指導が必要な理由

2022年から高校での金融教育が必修化されるなど、金融リテラシーの重要性が注目されています。
お年玉やお小遣いでお金に触れ始める小学生の時期から、正しいお金の使い方を学ぶことが大切です。
ここでは、小学生のうちからお金の使い方教育・指導が必要な理由について詳しく解説します。
将来子どもが自立して生活できるようにするため
小学生のうちからお金の使い方を教える理由の一つは、将来子どもが経済的に自立して暮らしていける力を育てることにあります。
子どもはいずれ社会に出て収入を得ますが、お金の価値や管理の方法を理解していなければ、安定した生活を築くのは難しくなります。
金銭感覚が未熟なまま大人になると、収入があっても無駄遣いが増え、生活に支障をきたす恐れがあるのです。
反対に、幼い頃から予算の立て方や貯蓄の習慣、欲しいものと必要なものの違い、働くことの意味を学んでおけば、収入を得るようになった後もお金を適切に管理できるでしょう。
こうして身につけた知識や習慣は、将来自分の力で生活を支えるための基盤となり、より安定した人生を送る土台となります。
子どもの将来の選択肢を広げるため
お金の仕組みを理解しておくことは、子どもの将来の選択肢を広げる大切な要素になります。
たとえば、限られたお小遣いの中でやりくりしたり、欲しい物を買うために我慢して貯金したりする経験を通して、計画的にお金を使う力が身につきます。
金融教育を受けた子どもは、必要な資金を自分で準備しやすくなり、進路の選択や夢の実現に向けて主体的に行動できるようになるのです。
さらに、金融知識があれば、進学や留学に向けた資金計画を立てるなど、可能性を広げられます。
一方で、お金に関する知識が不足すると将来のキャリア選択に影響を及ぼす可能性があります。
金融リテラシーを身につけておくことは、子どもが自分の興味や関心に沿った進路を選びやすくするための有効な手段といえるでしょう。
お金に関する悩みや不安を減らすため
お金にまつわる悩みや不安は、多くの人が抱える共通の課題です。
幼い頃からお金の基本を学んでいれば、大人になってから金銭面への苦手意識を和らげ、将来に対する漠然とした不安を軽減できる可能性があります。
たとえば、子どものうちに貯蓄や資産形成の大切さを理解していれば、結婚や住宅購入といったライフイベントに備えて計画的に資金を準備でき、老後に関する不安も小さくできるでしょう。
語学やスポーツと同じように、お金の知識も早い段階で習得するほど自信につながります。
その結果、将来の人生設計をより安心して描けるようになります。
小学生にお金の使い方を教えるときのポイント

小学生にお金の使い方を教えるときのポイントは、以下のとおりです。
- お金は「ありがとう」の対価であることを伝える
- お金の使い方と貯め方の基本を学ばせる
- 友達同士でもお金の貸し借りをしないと教える
- お金で困ったらすぐ大人に相談する習慣をつける
それぞれのポイントについて、下記で詳しく解説します。
お金は「ありがとう」の対価であることを伝える
子どもにお金の本質を理解させるためには、まず「お金はありがとうの対価である」という考え方を伝えることが大切です。
お金は人の役に立った結果、「助けてくれてありがとう」という気持ちとともに支払われるものであり、誰かに感謝された証と言えます。
両親が得る給料も、仕事を通して社会や人々の役に立ったことへの報酬です。
お金は自然に生まれるものではなく、家庭にあるお金も両親がどこかで「ありがとう」と交換して得た結果であると教える必要があります。
こうした考え方を身につければ、お金に対する感謝の気持ちと有限性の意識が育まれ、無駄遣いを控える姿勢にもつながります。
お金の使い方と貯め方の基本を学ばせる
子どもにはまず、お金の使い方と貯め方の基本を身につけさせることが重要です。
お金を貯める・使う力は金融教育の基盤となるスキルであり、小学生でも十分に習得できます。
貯める力を育てるには、実際に貯金を体験させるのが効果的です。
貯金箱を使えばお金が増えていく様子を視覚的に確認でき、達成感が得られるため継続につながります。
使う力を育てるには、欲しいものと必要なものを区別する習慣を持たせることが大切です。
さらに、お金の使い道を記録させることで、自分の消費行動を客観的に把握できます。
買い物の場面では、欲求と必要性を踏まえて優先順位を考えさせましょう。
また、子どもが自分で使ったお金については、一見無駄遣いに見えても叱らず、本人に管理を任せて経験から学ばせることが大切です。
こうした積み重ねが、計画的な金銭管理や貯蓄習慣の定着につながり、将来の自立に役立ちます。
友達同士でもお金の貸し借りをしないと教える
小学生になると友達と外出する機会が増え、周囲の影響で欲しいものが多くなる時期を迎えます。
だからこそ、友達同士でお金を貸し借りしないよう、早い段階で教えておくことが欠かせません。
お金の貸し借りはトラブルにつながりやすく、いじめや仲間外れに発展する恐れもあります。
家庭内のルールとして「仲の良い友達でもお金の貸し借りやおごりはしない」と決めておくと安心です。
実際に貸し借りが原因で友情が壊れたり、人のお金に頼る癖がついたりするケースもあります。
特に子どもは、困っている友達を助けたい気持ちからお金を貸してしまうことがあります。
その気持ちは否定せず受け止めたうえで、貸すのではなく大人に相談するよう促すことが大切です。
友達同士の金銭トラブルを未然に防ぐためにも、貸し借りをしないというルールを徹底して伝えましょう。
お金で困ったらすぐ大人に相談する習慣をつける
お金で困ったときには、すぐに大人へ相談する習慣を持たせることが大切です。
普段から家族に相談する癖をつけておけば、金銭トラブルを未然に防げるだけでなく、万が一巻き込まれても周囲の力を借りて早期に解決できます。
子どものうちは親が直接対応できますが、大人になると金額や内容が大きくなり、家庭だけで対処できないケースも少なくありません。
だからこそ、小さい頃から「困ったら必ず相談する」という姿勢を身につけさせることが重要です。
お金の話題を家庭内で日常的に取り上げ、タブー視しないこともポイントです。
日頃から自然に会話しておけば相談への心理的ハードルが下がり、子どもが悩みを抱え込みにくくなります。
結果として、トラブルが大きくなる前に適切な対応が取れるようになります。
特に友達同士でお金の貸し借りが発生した場合には、必ず親に報告させましょう。
小学生がお金の使い方を身につける家庭での具体的な方法

小学生がお金の使い方を身につける家庭での具体的な方法は、以下のふたつです。
- お小遣い制度のルールを決めて実践する
- 家族でお金や仕事について話し合う
それぞれの方法について、下記で詳しく解説します。
お小遣い制度のルールを決めて実践する
お小遣い制度は子どもの金融教育に役立つ方法として、多くの家庭で取り入れられています。
導入する際は各家庭でルールを明確にし、「必要なものは親が負担し、欲しいものは自分で購入する」「特定のお手伝いをしたら○円」といった約束を子どもと共有しておくことが大切です。
また、お手伝いに対してボーナスを与えるなどの工夫により、お金が労働の対価であることを実感させられます。
お小遣いの渡し方には主に定額制と報酬制があり、両者を組み合わせたハイブリッド型も活用できます。
それぞれの特徴を以下の表にまとめました。
| 方式 | メリット | デメリット |
| 定額制 | 計画的にお金を使う力が身につく | 苦労せず得られるため、お金のありがたみが薄れる |
| 報酬制 | お金は労働の対価であると理解できる | お小遣いがなければ行動しなくなる恐れがある |
| ハイブリッド型 | 双方の長所を取り入れられる | 親が仕組みを工夫する必要がある |
どの方式にも一長一短があるため、子どもの性格や家庭環境に合わせて選択してください。
特にハイブリッド型は柔軟性が高く、計画性と労働の意識を同時に育てやすい点で有効です。
ルールを曖昧にせず、親子でしっかり共有したうえで実践してください。
家族でお金や仕事について話し合う
日頃から家族でお金や仕事の話をすることは、子どもにとって「お金は話してはいけないもの」という意識をなくすうえで効果的です。
親が働いて収入を得ているからこそ生活が成り立っていることや、お金には限りがあることを自然に伝えていきましょう。
その際は否定的な言い回しを避け、「今月は○○にお金を使ったから家族で楽しめたね」といった前向きな表現を心がけると、子どもも素直に受け入れやすくなります。
お金に関する質問が出たときは「知らなくていい」と突き放さず、平均的な金額や仕組みを伝えながら一緒に考えてあげることが大切です。
また、親の仕事や収入について聞かれた場合も、できる範囲で隠さず説明し、社会とのつながりを理解させましょう。
日常の会話を通してお金の大切さや仕事の意味を語り合うことで、子どもが安心して相談できる雰囲気が家庭に育まれます。
日常の買い物に子どもを一緒に連れて行く
日常の買い物に子どもを連れて行くことは、金銭感覚を育てるうえで学びの場になります。
店頭で一緒に品物の値段を見比べたり、なぜその商品を選ぶのかを話し合いながら買い物したりすると、お金の使い方を自然に学ばせることができるのです。
たとえば、「夕食の食材を○○円以内で買う」という課題を与え、子どもに品物を選ばせれば、予算内でやりくりする力や価格差に気づく力が身につきます。
また「それは本当に必要なものか」「自分のお小遣いで買うならどうするか」と問いかけることで、欲しい物と必要な物を区別して考える習慣を養えます。
仮に欲しい物ばかり選んでお金が足りなくなったとしても、それは大切な経験です。
その場では「なぜ足りなくなったのか」を一緒に振り返り、次にどう工夫すれば良いかを考えさせることが、計画的なお金の使い方を学ぶ機会につながります。
遊びやゲームを通して金銭感覚を育てる
遊びやゲームを取り入れると、子どもは楽しみながら金銭感覚を身につけられます。
金融庁が公開している「うんこお金ドリル」は、クイズ形式でお金の仕組みやトラブルへの対処法を学べる教材です。
また、任天堂の「どうぶつの森」では、ものを売買してゲーム内通貨のベルを稼ぎ、貯金やローン返済を体験できます。
定番のボードゲーム「人生ゲーム」も、職業を選んで給料を受け取り、結婚や出産などのライフイベントに対応しながら出費を管理する仕組みを学べます。
家族で一緒にプレイするのはもちろん、子どもに遊ばせた後に「どう感じた?」と問いかけるのも有効です。
こうした体験を通して、お金を得る大変さや計画的に使う大切さを、遊びの中で自然に理解できるようになります。
小学生向け!お金の使い方を学べる教材・公的コンテンツの活用

小学生がお金の使い方を楽しく学ぶには、親しみやすい公的教材やコンテンツを活用することが効果的です。
多くは無料で利用でき、家庭や学校で簡単に取り入れられます。
金融庁・金融教育推進機構提供の教材、銀行のキッズ向けコンテンツ、絵本やアニメ動画など、さまざまな方法について詳しく解説します。
金融庁や金融教育推進機構の提供教材を利用する
金融教育推進機構(J-FLEC)の公式サイトでは、小学生から社会人まで幅広い世代を対象にした学習教材が無料で公開されています。
小学生向けの「おこづかいからまなぶお金の話」では、おこづかいの使い方や貯め方、お金の流れ、金融トラブルへの対応などをクイズ形式で学べる仕組みです。
また、金融庁が監修した「うんこドリル」シリーズとのコラボ教材も提供されており、子どもが親しみやすい形で金融の仕組みを理解できます。
さらに、金融庁のサイトには子ども向けパンフレット「くらしと金融」も公開されており、お金の流れや金融の役割をわかりやすく学べます。
公的機関の教材は信頼性が高く、無料で利用できる点がメリットです。
家庭や学校で積極的に活用すれば、子どもが安心して金融知識を身につけられる環境を整えられます。
銀行など金融機関のキッズ向けコンテンツをチェックする
金融機関でも小学生向けの金融教育コンテンツが提供されています。
日本銀行の子ども向け冊子「にちぎん☆キッズ」では、マンガを通して「お金とは何か」「お金の流れ」といったテーマをわかりやすく解説しており、銀行の役割を楽しく学べます。
さらに、物価の決まり方やインフレ・デフレといった仕組みにも触れており、価格の安定が社会にとってなぜ重要かを理解できる内容です。
ホームページから無料でダウンロードでき、親子で一緒に学習する教材として活用できます。
また、都市銀行や地方銀行でも、ホームページ上にキッズコーナーを設けたり、親子向けのマネー講座を開催したりする例があります。
なかには、貯金の大切さを伝えるクイズや動画を公開している銀行もあるのです。
金融機関のコンテンツをチェックすれば、子どもがお金や金融に興味を持ち、理解を深めるきっかけをつくれます。
絵本やアニメ動画で楽しくお金の大切さを教える
お金の話はどうしても難しく感じられがちですが、絵本やアニメ動画を取り入れれば、子どもにわかりやすく楽しく伝えられます。
かわいらしいキャラクターや物語を通して、子どもは自然にお金の役割や使い方を理解できるようになるでしょう。
たとえば、絵本「100円たんけん」では100円で買えるものを探しながら物の価値を考えることができ、「めいちゃんの500円玉」では貯金する喜びを学べます。
また、インターネット上で無料公開されている子ども向けの教育アニメには、大金を偶然手にした子どもたちが使い道に悩むストーリーなどがあり、お金の価値や正しい使い方を考えるきっかけを与えてくれます。
教材を親子で一緒に楽しめば会話も生まれ、堅苦しくならずに将来役立つ金銭感覚を身につけやすくなるでしょう。
小学生でお金の使い方を学ぶなら実践が一番

学校でも金融教育が始まりましたが、授業時間が短く、知識を教えるだけで実践がまだ不足しているのが現状です。
小学生が本当にお金の使い方を身につけるには、家庭や日常生活でお金を扱う実践経験が欠かせません。
小さな成功体験・失敗体験から学ばせる
子どもにお金の大切さを教えるには、成功体験だけでなく小さな失敗体験をさせることも欠かせません。
おこづかいを自由に使わせて失敗を経験させることで、金銭感覚や判断力が育ちます。
たとえば、一度に使いすぎて途中でお金が足りなくなれば、計画的に使う必要性を実感できます。
反対に、コツコツ貯めて欲しい物を買えたときには、大きな達成感を得られるでしょう。
小さな失敗から学ぶ経験は、大きな失敗を防ぎ将来の成功につながります。
親は子どもの失敗を過度に恐れず、安全な範囲であえて体験させることが重要です。
計画的に貯めて目標を達成する成功体験は、自信と意欲を高め、学びをさらに深めるきっかけになります。
月末にはおこづかい帳を親子で一緒に振り返り、うまくできた点は褒め、失敗した点は「どうすればよかったか」を考える習慣をつけましょう。
成功と失敗の両方から学ぶことで、健全な金銭感覚が自然と身についていきます。
金融教育の専門スクールを活用する
学校での授業に加え、専門の金融教育スクールを取り入れることも有効です。
学校だけでは、補いきれない部分をサポートする役割が年々大きくなっています。
金融教育専門スクール「MIRADAS(ミラダス)」では、子どもの発達段階に応じて基礎から応用まで体系的に学べるカリキュラムが用意されています。
知識を一方的に詰め込むのではなく、仮想投資ゲームやディスカッションを通して主体的に学べるのが特徴です。
楽しみながら実践的にお金の知識を身につけられる場として、小学生から高校生までを対象に注目を集めています。
保護者からは「実生活に役立つ知識を学べる」と好評で、少人数制や柔軟なスケジュールにより、他の習い事との両立もしやすい点も評価されています。
学校教育と組み合わせて活用すると、子どもの金融リテラシーをさらに高めることができるでしょう。
小学生からお金の使い方を学ぶならMIRADASがおすすめ!

小学生のうちにお金の使い方を学ぶには、机上の知識だけでなく、実際にお金を扱う経験を積むことが欠かせません。
おこづかいを通して成功や失敗を繰り返すなかで、子どもは楽しみながら金銭感覚を養い、大きな失敗を避ける判断力も育まれます。
ただし、家庭だけでは伝えにくい専門的な知識や実践スキルもあります。
その部分を補えるのが、金融教育の専門スクールです。
幼いうちからお金との付き合い方を学んでおけば、将来の金銭トラブルを防ぐことにもつながります。
MIRADAS(ミラダス)は学習塾が運営する金融教育スクールで、仮想投資などの実践的なプログラムを通して、楽しみながら学べる点が特徴です。
将来、自分で考え行動できる「お金に強い子」を育てる場として注目されており、評判も高まっています。
公式サイトから無料体験を申し込めるため、まずは親子で参加してみてください。