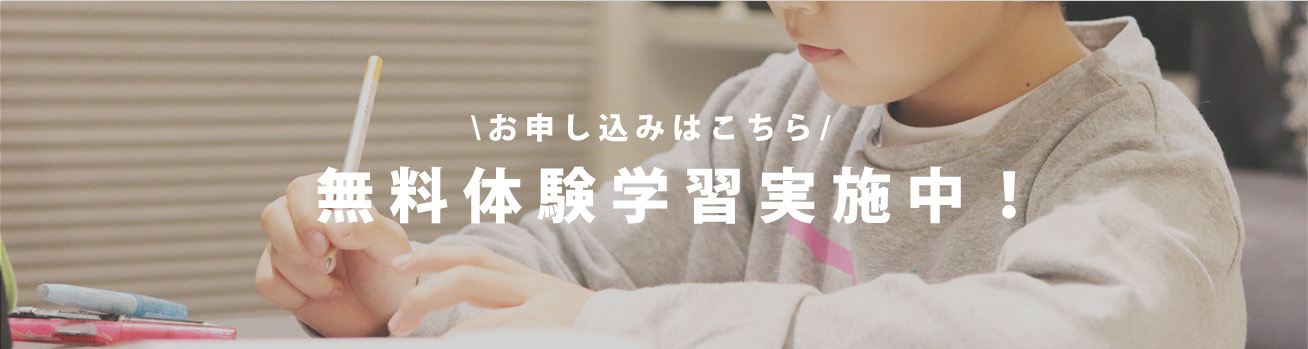2020年度から小学校で金融教育が義務化され、「うちの子の授業は大丈夫?」と不安を感じている保護者も多いのではないでしょうか。小学校では金融教育として独立した科目を勉強するのではなく、社会科などの既存教科と一緒にお金について学びます。
本記事では、小学校で義務化された金融教育について具体的な内容から家庭で今日から実践できる5つのステップまでを分かりやすく解説します。本記事を読めば、小学校の金融教育の内容を理解してスムーズに家庭でもフォローできるでしょう。お金について基本的な知識を身につけさせ、子どもが自立して生きられるようサポートしてください。
この記事のコンテンツ
小学校の金融教育義務化とは?いつから始まった?

金融教育とは、お金とのより良い関わり方を学び、社会のなかで自分らしく豊かに生きていくための力を養う教育です。小学校での金融教育は、2020年度から新しい学習指導要領のなかで必修化されました。
ただし、金融教育と呼ばれる名前の新しい教科が始まったわけではありません。実は、社会科や家庭科、総合的な学習の時間など既存教科のなかで各授業内容に合わせてお金の役割や大切さを学んでいく形が取られています。
例えば、社会科では買い物や商品の生産・販売の仕組みを学びます。そのなかで、お金が商品と交換するための便利な道具であることや価格が決まる仕組みなど金融の基本を学ぶ機会が設けられている状況です。
参考:金融教育のねらいと基本的性格|金融広報中央委員会
参考:小学校学習指導要領解説|文部科学省
金融教育が義務化された3つの社会的背景

金融教育が義務化された社会的背景として、以下の3つがあげられます。
- ・成年年齢の18歳への引き下げ
- ・キャッシュレス化の進展
- ・人生100年時代と資産形成の重要性
成年年齢の18歳への引き下げ
金融教育が義務化された背景として、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことがあげられます。つまり、高校3年生でも親の同意なしにひとりでさまざまな契約ができるようになったことを意味します。
例えば、スマートフォンやアパートを借りる契約、さらには高額な商品を購入するためのローン契約も子供ひとりで可能です。そのため、知識や経験が不十分なまま安易に契約を結んでしまうと、予期せぬ消費者トラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
成人になると未成年者取消権(民法5条)がなくなり、不利益な契約であっても契約後は取り消せません。だからこそ、契約の重みや社会的な責任について金融教育を通して早い段階から学ぶことが不可欠です。
参考:民法|e-Gov法令検索
キャッシュレス化の進展
キャッシュレス化の進展も、金融教育が義務化された要因のひとつです。親が子供だった頃と比べてお金の姿は大きく変わり、今や現金を持たずにスマートフォンひとつで買い物できます。
キャッシュレス決済は便利ですが、一方でお金を使っている実感が湧きにくい側面もあります。財布からお札・小銭が減っていく感覚がないため、特に子供たちはお金が無限に湧き出てくるかのように感じてしまうかもしれません。
目に見えないお金の価値を正しく理解し、計画的にお金を使う習慣を身につけることの重要性は、ますます高まっています。そのため、金融教育を通じてキャッシュレス社会に適応する金銭感覚を養うことが求められています。
人生100年時代と資産形成の重要性
人生100年時代における資産形成の重要性も、金融教育が義務化された背景のひとつです。医療の進歩により、私たちの寿命は今後さらに延びていくと予想されています。喜ばしい時代である一方、長い人生を豊かに暮らしていくためには計画的にお金と付き合っていく必要があります。
かつてのように、銀行に預けておくだけで安心と呼べる時代は終わりを告げ、自分の資産を守り育てていく資産形成の視点が不可欠となりました。もちろん、小学校の授業で株式投資の具体的な手法を学ぶわけではありません。しかし、お金には使う・貯めるだけでなく社会の役に立ちながら増やす役割もあると知ることは、将来の経済的自立に向けた基礎となります。
小学校で金融教育を学ぶ意義
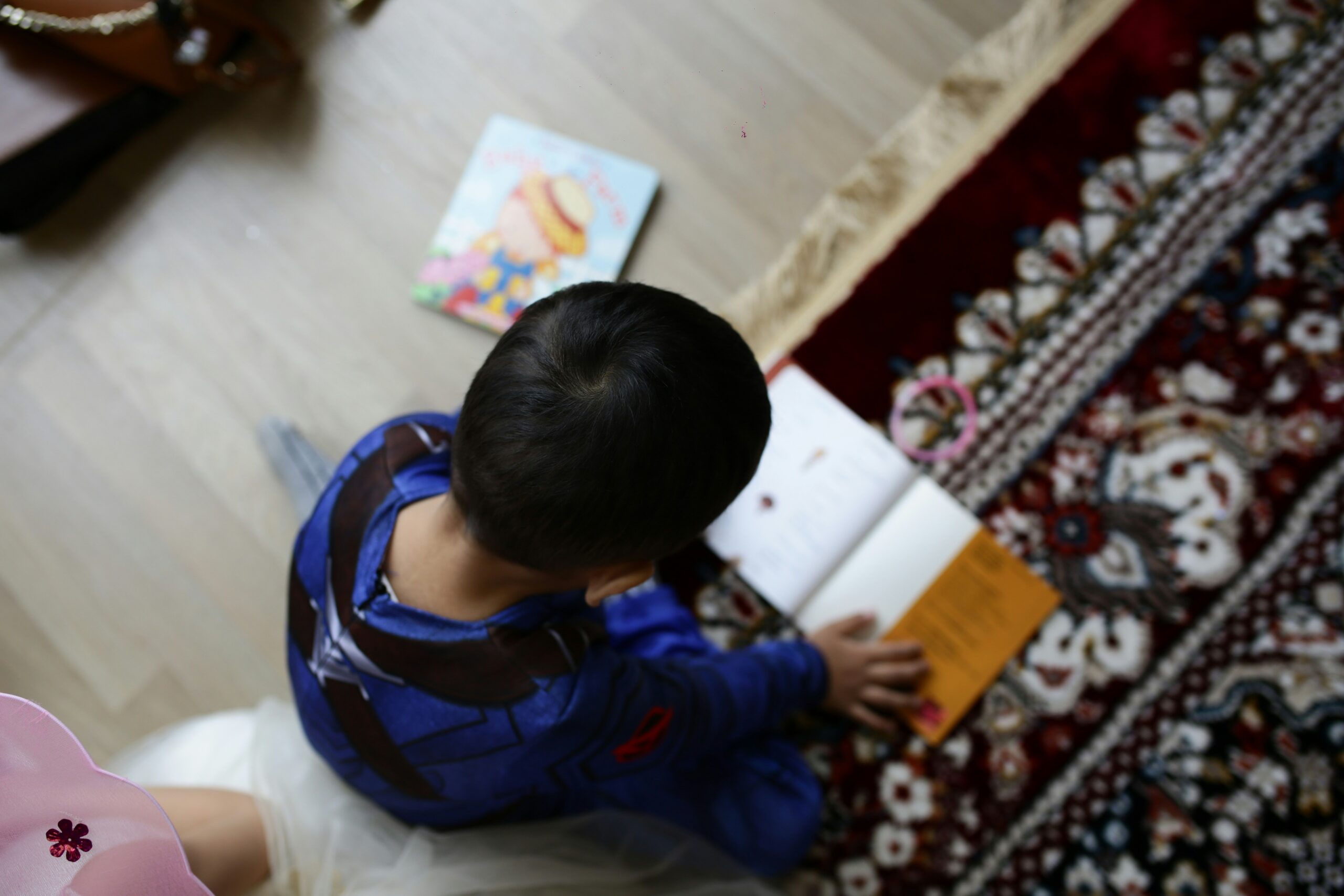
小学校で金融教育を学ぶ意義として、以下の3つがあげられます。
- ・自立して生きられる力が身につく
- ・社会との関わりを意識できる
- ・積極的に物事へ取り組むきっかけになる
上記のように数多くのメリットがあるため、早い段階からお金に関する基礎知識を身につけさせましょう。
自立して生きられる力が身につく
金融教育の意義は子供が将来経済的に自立し、自分らしい人生を設計していく力を築く点にあります。人間社会で生きていくにあたって、お金は決して切り離せません。お金に関する正しい知識や商品・サービスの価値を適切に判断する力は、人生の選択肢を広げて困難な状況を乗り越えるのに役立ちます。
例えば、限られたお小遣いを計画的に使う経験で、将来の家計管理能力の基礎を養うことが可能です。また、「欲しいものを手に入れるためにどうお金を貯めるか」を自分で考えるプロセスは、目標達成や問題解決の能力向上にもつながります。
社会との関わりを意識できる
お金について学ぶことは子供が社会の仕組みを理解し、自分の役割やつながりを意識する絶好の機会です。普段何気なく使っているお金が「どこから来てどこへ行くのか」を学べば、自分ひとりの世界から視野がぐっと広がります。
例えば、「お店でお菓子を買う」などの身近な行動を考えてみましょう。支払ったお金がお店の人やお菓子をつくった会社の人の給料になり、一部は税金として納められて道路や公園の整備に役立てられます。上記の流れから、自分が支払うお金が誰かの役に立ち、社会を動かす一翼を担っている事実が分かります。
積極的に物事へ取り組むきっかけになる
金融教育は、子供の学習意欲や物事への主体性を引き出す効果も期待できます。身近なお金を通して日々の学習に取り組めば、勉強として習う算数や社会科が実生活と密接に結びついている事実を実感できるためです。
例えば、お小遣いを貯めて欲しいものを買う目標は子供にとって分かりやすくモチベーションを高めます。また、お小遣いを貯めて欲しいものを買う目標を達成するためには、以下のような手順を経る必要があります。
- 1.目標達成のために、値段を比較検討する(情報収集・分析)
- 2.どうすれば効率よく貯金できるか計画を立てる(論理的思考)
- 3.時には親の手伝いをして労働の対価を得る(勤労観)
上記のように、受け身の学習ではなく子供が自ら考えて行動する楽しさを知れるため、知的好奇心を刺激する絶好の機会となります。
小学校の金融教育で具体的に学ぶ内容

以下では、金融庁が公開している指導要領を参考に、低学年・中学年・高学年で学ぶ内容の目安を具体的にご紹介します。
- ・小学校低学年(1・2年生):お金の役割・価値について学ぶ
- ・小学校中学年(3・4年生):お金の使い方・管理について学ぶ
- ・小学校高学年(5・6年生):お金と生活・社会との関わりについて学ぶ
参考:金融教育プログラム「学校における金融教育の年齢層別目標」|金融広報中央委員会
小学校低学年(1・2年生):お金の役割・価値について学ぶ
小学校低学年(1・2年生)の学習ゴールは、お金の基本的な役割と大切さを知ることです。1年生や2年生は、お使いを頼まれたり、自分でお菓子を買ったりと初めてお金に触れる機会が増える大切な時期です。
上記の段階では難しい経済の話ではなく、実生活に即した体験を通してお金の基本を学びます。小学校低学年のお金に関する具体的な学習内容の例は、以下の通りです。
| 学習テーマ | 学習内容 |
| お金の種類 | 硬貨や紙幣にはさまざまな種類があることを学ぶ |
| 買い物の仕組み | 「もの」と「お金」を交換する仕組みを、お店屋さんごっこなどを通じて体験的に学ぶ |
| お金の大切さ | お金は誰かが働いて得た大切なものであることを理解し、大切にする心を育む |
家庭では買い物の際に値段を確認したり、お手伝いを通じて感謝の気持ちを伝えたりすることがお金の学習につながります。
小学校中学年(3・4年生):お金の使い方・管理について学ぶ
小学校中学年(3・4年生)の学習ゴールは、計画的なお金の使い方と管理の基礎を身につけることです。お小遣いを定期的にもらい始める子供も増える中学年では、より実践的なお金の管理能力を養っていきます。
具体的には、欲しいものと必要なものの違いを自分で考え、判断する力を身につけます。お金の使い方・管理について小学校中学年で学ぶ具体的な内容の例は、以下の通りです。
| 学習テーマ | 学習内容 |
| 計画的な買い物の仕方 | 限られた予算のなかで、優先順位をつけて買い物をする計画を立てる |
| 貯蓄の目的と方法 | 欲しいものを手に入れるために、目標を立てて貯金する経験を積む |
| お金の管理 | お小遣い帳などを使い、自分のお金の出入りを記録し、把握する習慣をつける |
上記のような小学校中学年で実施する金融教育は、将来の家計管理の第一歩です。「今月はお金を使いすぎたから、来月は少し我慢しよう」などの試行錯誤の経験が、子供の金銭感覚を豊かにしていきます。
小学校高学年(5・6年生):お金と生活・社会との関わりについて学ぶ
小学校高学年(5・6年生)の学習ゴールは自分と社会のつながりを意識し、消費者としての責任を理解することです。お金の使い方だけでなく、「社会全体でどのように循環しているのか」を学び、経済の仕組みへの関心を深めていきます。小学校高学年での具体的な学習内容の例は、以下の通りです。
| 学習テーマ | 学習内容 |
| 多様な支払い方法 | 現金だけでなくクレジットカード・電子マネーなどのキャッシュレス決済の仕組みと利便性・注意点を学ぶ |
| 消費者としての役割と責任 | 商品・サービスを選択する際の視点(価格、品質、環境への影響など)や契約の重要性について学ぶ |
| 税金の役割 | 消費税などの税金が警察、消防、学校教育などの公共サービスを支えるために使われていることを理解する |
小学校高学年でのお金に関する学びは、中学校の公民科で学習する「市場経済の仕組み」などより専門的な内容の基礎にもなります。
小学校における金融教育の課題
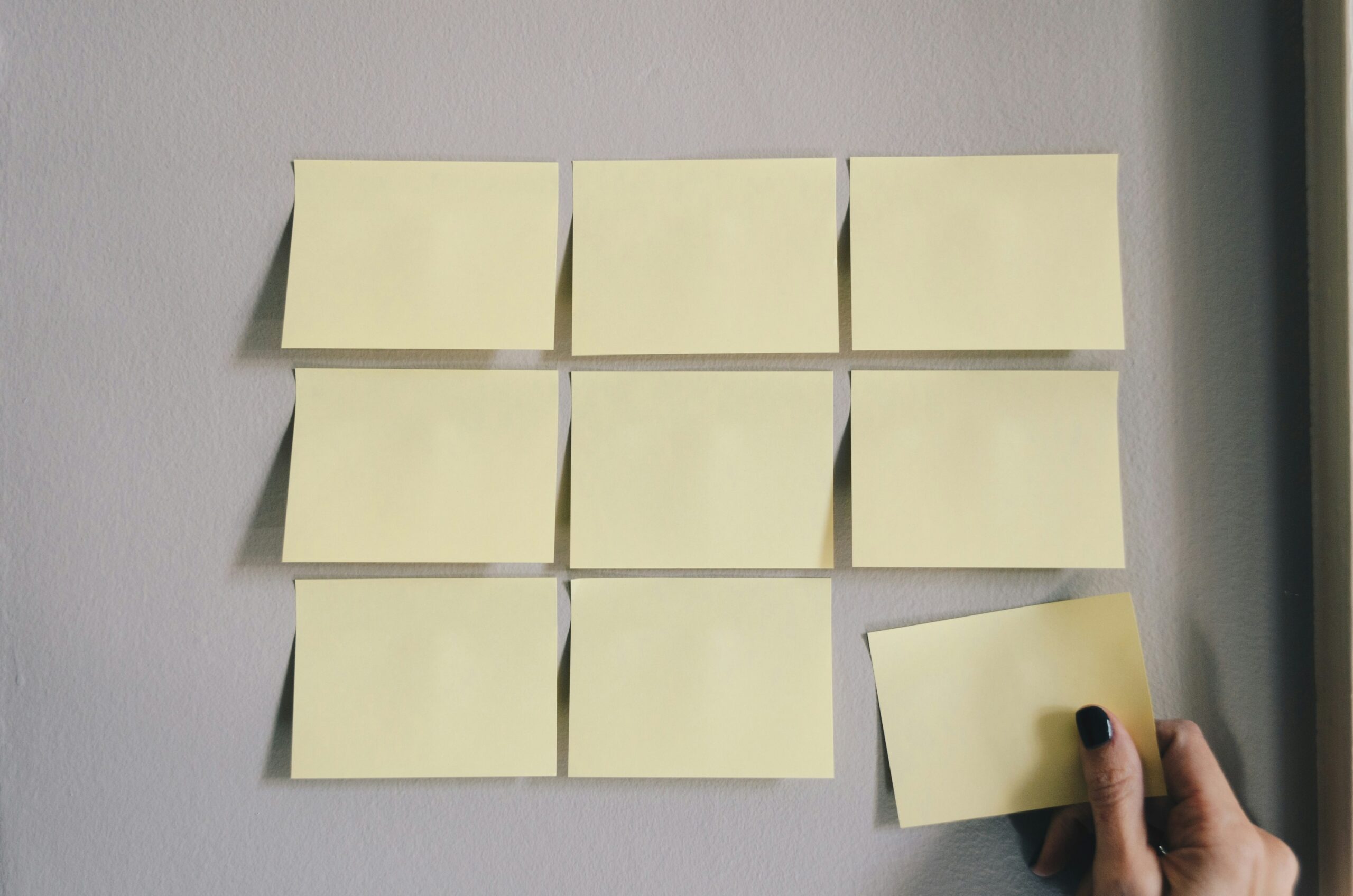
小学校で金融教育が義務化され、学習環境は整ってきたものの以下のような課題もあります。
- ・授業時間と内容の限界
- ・教員の専門性と熱意の差
- ・自分ごととして捉えにくい集団教育の壁
保護者が上記の課題を理解しておくと、家庭でのサポートがやりやすくなります。
授業時間と内容の限界
まず課題としてあげられるのが、授業時間と扱える内容に限りがある点です。金融教育は独立した教科ではなく、社会科や家庭科などの既存教科に組み込まれて行われます。そのため、各単元で金融教育に割ける時間はどうしても限られてしまいます。
例えば、社会科の授業で税金の役割について学ぶ時間は、年間を通じてもわずかな時間しかありません。そのなかで、税金の基本的な仕組みや使われ方を学べますが、一人ひとりのライフプランに関わる踏み込んだ内容まで扱うのは難しいのが現状です。学校での金融教育は、あくまで金融や経済の基本的な仕組みを知る入り口の役割であると捉えましょう。
教員の専門性と熱意の差
次に、指導する教員による差が生まれやすい課題もあげられます。小学校の先生は教科指導のプロですが、必ずしも全員が金融や経済に関する専門的な知識を深く持っているわけではありません。新しい学習指導要領のもと先生も研修などを通じて学ぶものの、金融・経済の知識や指導経験には個人差が生じます。
また、先生自身の金融教育に対する関心や熱意によって授業の質が変わってくる可能性も否定できません。あるクラスでは実生活に即した具体例で盛り上がる一方、別のクラスでは教科書を読むだけの授業になるなどの差も考えられます。
自分ごととして捉えにくい集団教育の壁
学校で行う集団教育の特性上、お金の話を自分ごととして捉えさせるのが難しい側面もあります。お金に関する価値観や状況は各家庭によって大きく異なり、お小遣いの金額やルール、家庭での金銭教育方針もさまざまです。しかし、学校の授業では個別の家庭事情に合わせた指導はできません。
そのため、授業で学ぶお金の話が一般的な知識としては理解できても、自分の生活と直結したリアルな問題として感じにくい場合があります。例えば、「お小遣いを計画的に使おう」と教わっても、そもそもお小遣いをもらっていなければ、大切さを実感するのは難しくなります。
今日から家庭で始められる金融教育5ステップ

ここでは、今日からでもすぐに始められる家庭での金融教育の具体的な5つのステップを紹介します。
- ・ステップ1:お金のありがたみを体感させる
- ・ステップ2:お小遣いでやりくりする力を養う
- ・ステップ3:買い物体験で価値を見抜く目を育てる
- ・ステップ4:親子でお金の使い道を話し合う
- ・ステップ5:お金を増やす・守るの基礎に触れる
小学校での金融教育の義務化を良い機会と捉え、日々の生活のなかにお金について学ぶ仕組みを取り入れましょう。
ステップ1:お金のありがたみを体感させる
最初のステップでは、お金が労働の対価であると体験から学ばせましょう。具体的には、家庭でのお手伝いを活用するのが効果的です。
例えば、お風呂掃除や窓拭きなどのお手伝いを子供にお願いし、達成できたら報酬として少額のお金を渡してみましょう。また、子供にお金を渡す際は以下のポイントを意識すると効果的です。
- ・「ありがとう」と感謝の言葉とともに渡す
- ・お父さんやお母さんが毎日お仕事をしてお給料をもらっていることとつなげて話す
上記の体験を通じて、お金は無限に湧いてくるものではなく、誰かの頑張りによって得られるものだという感覚が子供に自然と芽生えます。
ステップ2:お小遣いでやりくりする力を養う
次に、お小遣い制度を導入して自分のお金でやりくりする経験を積ませましょう。単にお金を与えるのではなく、管理能力を育てることを目的に以下の点を意識してお小遣い制度を導入するのがおすすめです。
| 取り組み | 育まれる力 |
| 定額のお小遣いを定期的に渡す | 予算内でどう使うかという計画性 |
| 親子で使い道のルールを決める | 「欲しいもの」と「必要なもの」を区別し、優先順位をつける判断力 |
| お小遣い帳をつける | お金の流れを「見える化」し、自分の消費行動を客観的に振り返る力 |
お小遣い制度を導入するうえで最も大切なのは、失敗を恐れずに子供の判断に任せることです。もし月の初めにお金を使い切ってしまっても安易に追加で渡さず、失敗から学ばせましょう。なぜなら、小さな失敗の痛みこそが、計画的にお金を使うことの重要性を教える何よりの学びとなるためです。
ステップ3:買い物体験で価値を見抜く目を育てる
続いて、子供と一緒にスーパーへ行き、買い物を積極的に体験させてみましょう。学習の観点からは、買い物する際に「カレーをつくるから、1,000円以内で材料を買うのを手伝ってくれる?」と課題を与えるのがおすすめです。また、「同じお菓子でも、こっちのお店の方が少し安いね。どうしてだろう?」と一緒に考えたりするのも効果的です。
子供と買い物する際には、お金について学ぶ観点から以下のポイントも意識しましょう。
- ・商品の値段を比較させる
- ・欲しいものか必要なものかを問いかける
実体験の積み重ねが、広告や周りの意見に流されず自分なりの基準で物の価値を判断する力を養います。
ステップ4:親子でお金の使い道を話し合う
親子でお金の使い道を話し合うのも、金融教育の観点からおすすめです。日本では「お金の話はタブー」の風潮が根強く残っていますが、家庭内ではぜひオープンに話す機会をつくってみてください。
もちろん、家庭の収入や貯蓄額を詳細に話す必要はありません。「おばあちゃんの誕生日に、みんなでお金を出し合ってプレゼントを買わない?」などの会話で十分です。なお、親子でお金の使い道を話し合う際は以下のポイントも意識しましょう。
- ・家族の目標のためにお金を使う楽しさを共有する
- ・寄付やプレゼントなど誰かのために使うお金の尊さを教える
お金は自分のためだけでなく、家族や誰かを幸せにするための道具でもあることを学べます。
ステップ5:お金を増やす・守るの基礎に触れる
最後のステップとして少し視野を広げ、お金を増やす・守る側面にも触れてみましょう。具体的には、小学校高学年になった段階で子供名義の銀行口座を一緒につくりに行くのがおすすめです。「銀行にお金を預けておくと、利息で少しだけお金が増えるんだよ」と教えてあげるのも良い経験になります。
また、お金を守る視点も重要で、下記のように消費者トラブルから身を守るための知識を伝えておきましょう。
- ・「絶対に儲かる」「クリックするだけでお金がもらえる」などの甘い話は、危ない詐欺かもしれない
- ・おかしいなと思ったら、必ずお父さんお母さんに相談する
より本格的な学びを求めるなら金融塾の選択肢も

小学校での金融教育の義務化をきっかけに、家庭でもお金について学ぶ機会が増えています。しかし、家庭で教育を進めるなかで「もっと体系的に教えてあげたい」「専門的な質問に答えられない」と感じる場面も出てくるかもしれません。
子供がお金や経済に強い興味を示した場合や、より本格的な学びの機会を与えたいと考えるなら「金融塾」を検討するのがおすすめです。以下では、家庭での金融教育では難しい側面や金融塾で得られるメリットを中心に説明します。
家庭教育だけでは難しいこと
家庭での対話を通じた金融教育は大切ですが、難しい側面がある点も事実です。例えば、親が金融の専門家でない場合、教える知識が断片的になったり、自身の経験に基づいた価値観に偏ってしまったりします。また、社会全体の経済の仕組みや将来の資産形成につながる考え方まで、お子さんにかみ砕いて教えるのは簡単なことではありません。
仕事など日々の忙しさで、継続的に子供との学びの時間を設ける難しさもあります。上記のような家庭教育の限界を補い、子供の可能性をさらに広げるのが金融塾の役割です。
金融塾で得られるメリット
金融塾では、家庭や学校だけでは得られない専門的かつ体系的な学びの機会が提供されており、以下のようなメリットがあります。
| メリット | 詳細 |
| 専門家による質の高い指導 | 金融知識が豊富なプロの講師が、子供の知的好奇心を引き出しながら正しい知識を分かりやすく指導してくれる |
| 体系立てられたカリキュラム | ・お金の基本から経済の仕組み、投資の基礎まで網羅的に学べる・発達段階に合わせた段階的なカリキュラムで無理なく知識を積み上げられる |
| 同じ興味を持つ仲間との出会い | ・同年代の仲間と一緒に学ぶ経験が大きな刺激になる・意見交換や議論を通じて、多角的な視点やコミュニケーション能力も養われる |
金融知識が豊富なプロが子供の発達状況に応じて指導してくれるため、小学校および家庭だけでの教育よりも効率的にお金に関する知識を学べます。
実践的な金融教育なら「金融塾MIRADAS」がおすすめ
数あるサービスのなかでも、特に実践的な学びを重視するなら「金融塾MIRADAS」がおすすめです。MIRADASは小学生から高校生を対象とした新しい形の金融塾で、ゲームのように楽しみながら経済の仕組みやお金の大切さを体験的に学べます。
また、単なる知識の詰め込みではなくディスカッションや投資体験を通じて、子供たちが主体的に学べるカリキュラムが組まれています。経験豊富な講師陣が、生徒一人ひとりに合わせた少人数制レッスンで丁寧にサポートできる点も強みです。
小学校での金融教育をきっかけに芽生えた子供の興味を、将来にわたって役立つ本物の力へと育てたいと考えている親も多いでしょう。ぜひ一度、金融塾MIRADASのプログラムを覗いてみてはいかがでしょうか。学習プログラムの詳細が気になる方は、気軽に以下のリンクからお問い合わせください。
小学校での金融教育義務化について
2020年度から、小学校で金融教育の義務化がスタートしています。キャッシュレス化や成年年齢の引き下げなどの社会変化を背景に、子供が将来お金に困らず豊かに生きるための土台づくりが学校で始まっています。
学校では年齢に応じてお金の役割から社会の仕組みまでを学びますが、授業時間や専門性の面で限界があるのも事実です。そこで重要なのが、学校での学びを子供自身の生きる力に変えるための家庭でのサポートです。
本記事で紹介したお小遣いのルールづくりや一緒の買い物体験、家族会議でのお金の話などは、今日からすぐに実践できる項目ばかりです。小学校での金融教育を絶好の機会と捉え、子供の未来のために家庭でのお金との付き合い方を見直してみてはいかがでしょうか。