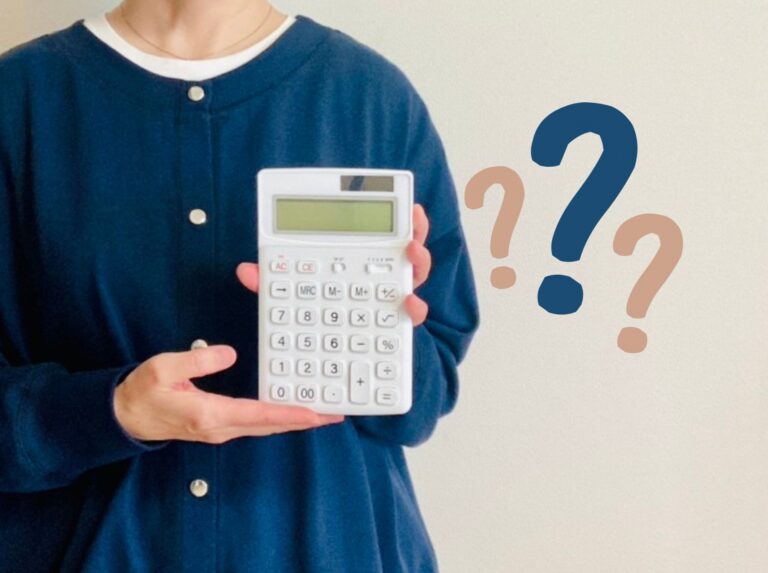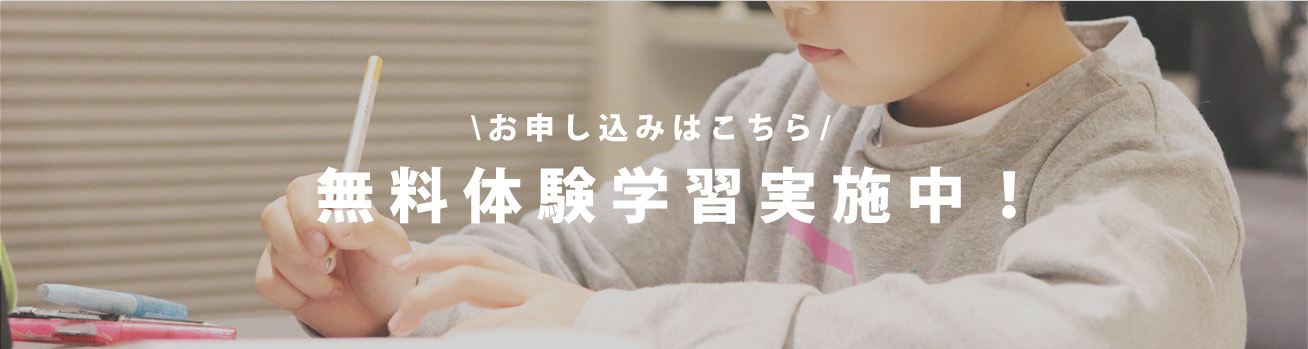「このジュース、今日は安い!」
「この文房具、思ったより高いなあ…」
お店で買い物をしていると、こんなふうに“値段”について感じることがありますよね。
でも実は、その「値段」にはちゃんと理由があるのです。
この記事では、子どもにもわかりやすく、「価格がどう決まるのか」「安さ・高さの裏にある社会や経済の仕組み」について解説します!
この記事のコンテンツ
「値段」と「価値」は同じじゃない?

価値が高い=値段が高い?
たとえば、世界に1枚しかないサッカー選手の直筆サイン入りユニフォームがあるとします。
もしそれを欲しがる人が100人いれば、値段は高くなるでしょう。
でも、誰も欲しがらなければ、たとえすごく貴重でも売れないかもしれません。
つまり、「価値がある=値段が高い」ではないのです。
値段は、欲しい人の多さ(需要)と、モノの数(供給)によって決まります。
値段を決める3つの大きな要素

① 需要と供給(じゅようときょうきゅう)
▷ 需要(じゅよう):ほしい人の数
人々が「これがほしい!」と思えば思うほど、需要は高くなります。
たとえば、暑い夏の日にはアイスの需要が増えます。
▷ 供給(きょうきゅう):モノの数
供給とは「その商品がどれくらい出回っているか」です。アイスの在庫が少なければ、同じアイスでも値段が上がることがあります。
💡【ポイント】
・需要が多くて供給が少ない=値段が高くなる
・需要が少なくて供給が多い=値段が下がる
② 原材料や人件費
パン1個を作るのにも、小麦粉・砂糖・卵などの材料費がかかりますし、それを作る人の労働力(=人件費)も必要です。
また、店で売るためには電気代や運搬費もかかります。
これらのコストが上がれば、商品の値段も上がるのは自然なことです。
③ ブランドやイメージ戦略
有名なブランドの服やバッグは、素材だけでなく「信頼」や「デザイン性」にも価値があるとされます。
そのため、同じような見た目でも、ノーブランドの商品より数倍高いこともあります。
「あれ?なんでこんなに高いの?」日常の価格のナゾ

コンビニとスーパーで違う理由
同じ500mlのジュースが、スーパーでは98円、コンビニでは150円。
こ同じ500mlのジュースが、スーパーでは98円、コンビニでは150円。どうしてこんなに差があるのでしょう?
・コンビニは24時間営業で便利
・駅の近くや街中など、立地がよくてすぐ買える
・品ぞろえや人件費、家賃が高いため価格に上乗せされる
つまり「便利さの分、少し高くなる」のです。
季節によって変わる価格
冬になると白菜や鍋の具材が高くなるように、「旬」や「気候」によって野菜や果物の価格は上下します。
台風で野菜が取れなくなった年などは、スーパーでレタス1玉300円を超えることもあるほどです。
「買う前に考える」力を育てよう!

安いものには理由がある
「100円で買えるならラッキー!」とすぐ手を伸ばす前に、「なぜ安いのか?」を考えてみましょう。
・賞味期限が近い
・売れ残りの在庫処分
・原価が安い素材を使っている
これらの要因を知ると、「本当に必要か?」「長く使えるか?」といった目線も育ちます。
高くても価値があることも
逆に、少し高くても長く使える文房具や、環境に配慮されたフェアトレード商品など、「高いけど意味のある買い物」も存在します!
保護者向けワンポイント|“値段の理由”を一緒に考える習慣を

買い物の場面で、「これちょっと高いね。なんでだろう?」と親が問いかけるだけで、子どもは自然と価格に関買い物のとき、「このジュース、コンビニだと高いね。なんでだと思う?」など、声かけするだけで、子どもは“値段のしくみ”に自然と関心を持つようになります。
・チラシで価格を比較してみる
・セール品の意味を話し合う
・「高くても買いたいモノってなんだろう?」をテーマに会話する
買い物の場は、楽しい“経済の授業”のチャンスです!
まとめ|値段には、ストーリーがある

・値段は「需要と供給」「コスト」「ブランド価値」など複数の要素で決まる
・安さの裏には理由がある、高さにも価値がある
・子どもが価格を「考える習慣」を持つことが、賢い消費者への第一歩
“値段を見る目”を持つことは、将来の「賢く生きる力」につながります。
日常のちょっとした買い物から、子どもたちの金融リテラシーを育てていきましょう!