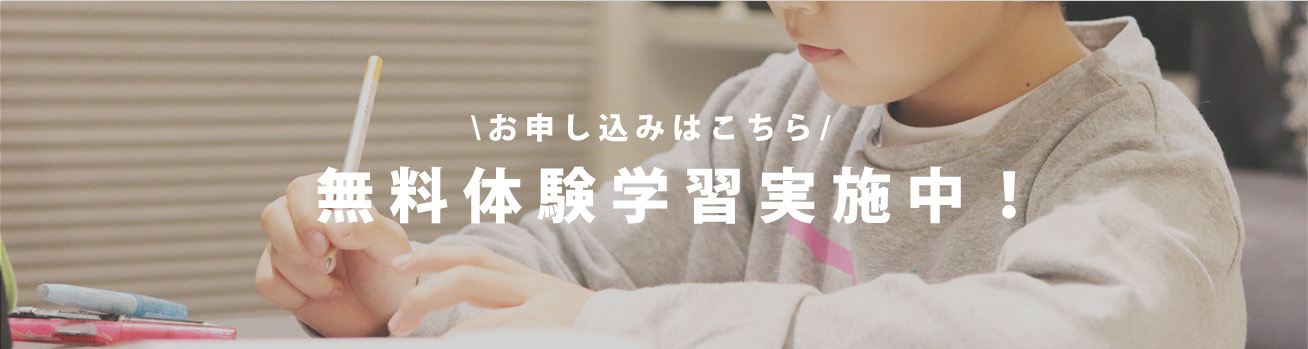「キャッシュレスで買い物が当たり前になってきたけど、うちの子はお金の価値をちゃんと理解しているのかな…?」
電子マネーやスマホ決済が広く普及し、「お金に触れない社会」が当たり前になった今、子どもの金銭感覚にどう向き合うべきか、多くの保護者が悩んでいます。
本記事では、キャッシュレス社会の特徴とそれが子どもに与える影響、そして親ができる実践的な教育方法についてわかりやすくご紹介します。
この記事のコンテンツ
キャッシュレスってどういうこと?

キャッシュレスとは、現金を使わずに支払いを行う方法のこと。
主な手段としては次のようなものがあります
・電子マネー(Suica、PASMOなど)
・QRコード決済(PayPay、LINE Pay、楽天Payなど)
・クレジットカード・デビットカード
・スマホ決済(Apple Pay、Google Pay など)
これらは財布からお札や小銭を出すことなく、タッチやスキャンだけで支払いが完了する便利な手段です。
なぜ今、キャッシュレスが増えているの?
・レジ対応が早く、スムーズ
・ポイントがたまりやすい
・感染対策として現金を避けたい
・財布を持ち歩かなくてもOK
このような理由から、キャッシュレスはますます日常生活に溶け込んでいます。
子どもにとってのキャッシュレスの落とし穴

お金が「減る感覚」が育ちにくい
キャッシュレス決済は便利な一方で、子どもが「お金を払っている」という実感を持ちづらいというデメリットがあります。
手現金を使えば、1000円札が減る・財布が軽くなるという視覚的な変化がありますが、キャッシュレスはその「実感」が希薄です。
その結果、「どれくらい使ったのか?」「あといくら残っているのか?」が把握しづらく、浪費につながることもあります。
「無料」と「後払い」の混同
スマホアプリやゲームの“無料お試し”が、いつの間にか課金に変わっていた…
サブスクも一度契約すると、解約しない限り料金が自動的に発生します。
こうした仕組みは、子どもにとって“お金の仕組みの見えにくさ”を助長させる原因になっています。
保護者ができる「キャッシュレス教育」の工夫

使った金額を“見える化”する
現金に触れないからこそ、支払いの内容を記録・確認する習慣が必要です。
た現金を使わないからこそ、「記録する習慣」が大切です。
たとえば以下のような方法を取り入れてみましょう
・Suicaの利用履歴を親子で確認する
・スマホ決済の利用明細を一緒にチェック
・使った金額を紙やアプリでグラフ化する
「500円使ったから、残りはいくら?」という感覚を“数字で可視化”することで、金額の重みを感じやすくなります。
上限金額とルールを設ける
・月1000円まで
・ゲーム内課金は月1回まで
・コンビニは週2回までにする
こうしたルールをあらかじめ設けることで、子どもは「限られた予算の中でどう使うか?」を考える力が育まれます。
大切なのは、“制限”ではなく“選択”の機会を与えることです。
キャッシュレスでも「貯める力」を育てる
キャッシュレス=貯金できない、ではありません。
・銀行アプリで「目標貯金額」を表示
・デジタル貯金箱やスマホ連動型の残高表示機能を活用
「お金が減る感覚」と同じように、「お金が増えていく感覚」をデジタルでも体験させましょう。
キャッシュレスを学ぶ“体験”をつくる

模教育は「知識」だけでなく「体験」も大事です。
● 実践例
・Suicaに毎月1,000円チャージ → 使った分を記録して、翌月までに残っていたらボーナスをプレゼント
・仮想通貨やポイント制のゲームを活用して「価格の変動」や「使うと減る感覚」を知る(※投資を勧めるものではありません)
体験を通じて学ぶことで、子ども自身が「使い方」に対する責任感や判断力を身につけていくようになります。
まとめ|キャッシュレス時代の金銭教育は「見えないお金」を意識させることから

・キャッシュレスは便利な反面、「お金が減る感覚」が育ちにくい
・保護者の関わり方次第で、子どもにも金銭感覚をしっかり育てられる
・記録・ルール・体験の3つを軸に、家庭で「お金を意識する機会」を増やすことが重要
現代は「お金が見えない時代」です。
だからこそ、見えないお金とどう向き合い、どう使うのかを親子で一緒に考える時間が大切です。
便利なツールに頼るだけでなく、「使いすぎない工夫」「貯める楽しさ」「選ぶ責任」など、子どもにとっての“使う力”を育てていきましょう。
お金は、見えなくても確実に減っていきます。
そして、上手に使えば、未来を豊かにする道具にもなります。
そのバランス感覚こそ、キャッシュレス社会を生き抜くための“現代の金銭教育”なのです。