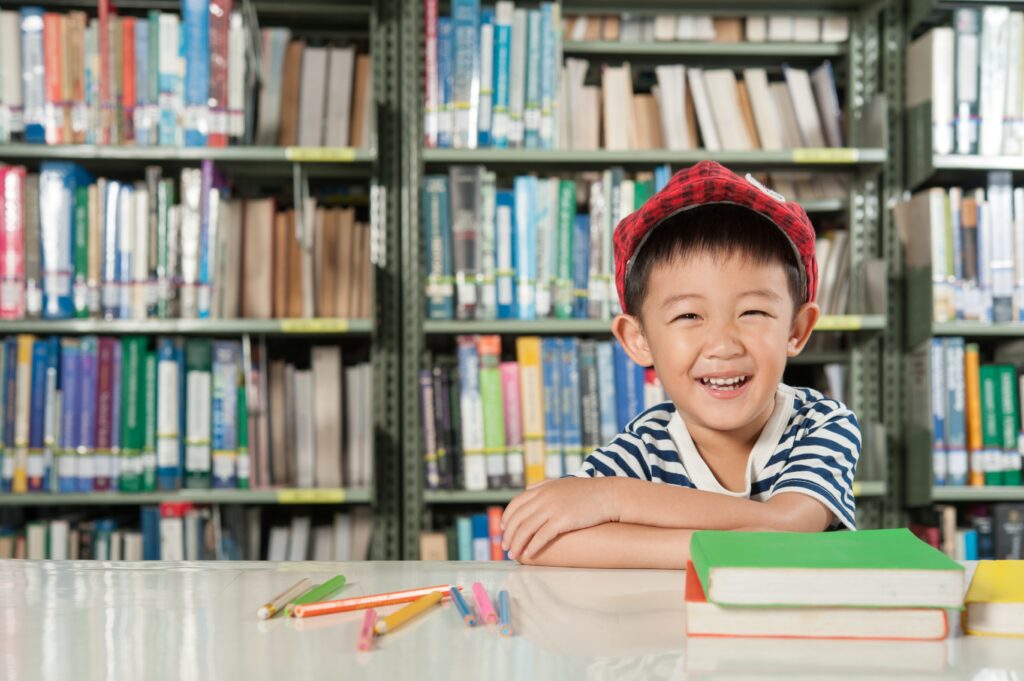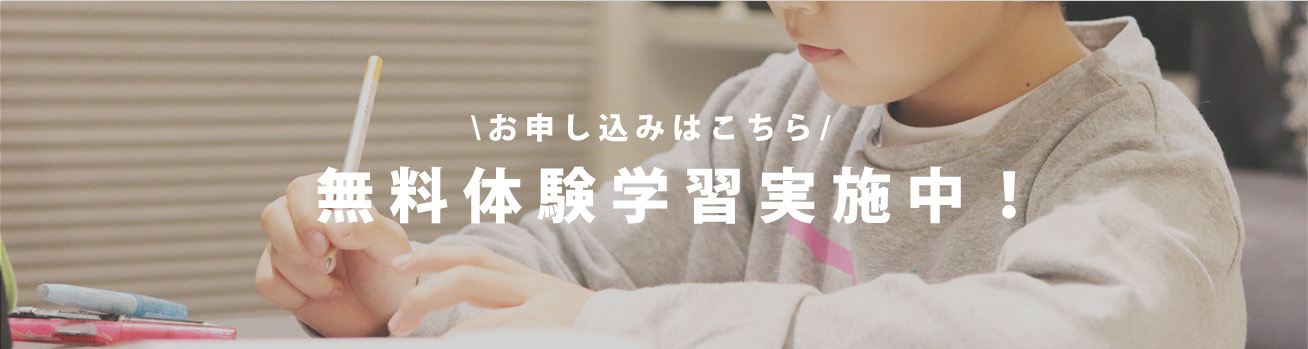みなさんは「税金」と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべますか?
税金は学校の机や椅子、通学路の信号機、病院や消防など、多くの身近な設備やサービスに使われています。
しかし、「中学生にも関係あるの?」「どのような種類があるの?」と疑問に思うこともあるでしょう。
この記事では、税金の基本や種類、使いみちなどについて、わかりやすく解説します。
この記事のコンテンツ
税金とはどのようなお金?詳しく説明!

国税と地方税のちがい
税金は、学校や道路、警察や消防など、安心して暮らせる社会の仕組みを支えるお金です。
働いてお給料をもらったり、買い物をしたりすると、その一部を税金として国や地域に納めます。
なお、税金には大きく分けて「国税」と「地方税」の2種類があります。
どちらも社会を支えるために欠かせませんが、使われ方と集め方が異なります。
・国税
国に納める税金です。
防衛や外交活動、国立大学や研究機関の運営など、国全体の仕組みを整えるために使われます。
国が直接管理するために規模が大きいのが特徴です。
【代表的な国税】所得税、法人税、贈与税
・地方税
都道府県や市区町村に納める税金です。
地域のゴミ収集や福祉など、生活に近い分野を支えるために使われます。
地域で快適に暮らすためには欠かせない財源です。
【代表的な地方税】住民税、固定資産税、自動車税
税金と公共料金の違い
税金と混同されやすいのが「公共料金」です。
その違いを詳しく見てみましょう。
・税金
国や自治体に納めるお金です。使い道は選べません。
みんなで出し合い、みんなのために使われます。
・公共料金
電気や水道などの公共サービスを利用した人が支払うお金です。
電気をたくさん使えば電気代が上がるように、利用量に応じて支払う金額は変わります。
税金を払う理由

公共サービスを支える
税金を払う大きな理由のひとつは、社会に必要なサービスを支える財源にするためです。
学校や公園などは誰もが利用しますが、個人では準備や運営ができません。
そのため、みんなで少しずつ「税金」という形でお金を出し合い、誰でも安心して利用できるサービスを整えます。
なお、災害が起きたときの避難所や復興支援も税金でまかなわれています。
税金があるからこそ、社会全体で助け合う仕組みが成り立つと考えていいでしょう。
所得の再分配
経済的な格差を小さくするのも税金を払う理由のひとつです。
社会には、収入が多い人もいれば、さまざまな事情で収入が少ない人もいます。
対策をしなければ、一部の人だけが豊かになり、所得の格差が大きくなる恐れもあるでしょう。
そのため、収入の多い人には多くの税金を負担してもらい、医療費の補助や子育て支援などに使います。
たくさん稼いだ人が余計に払うのは不公平と感じるかもしれません。
しかし、弱い立場の人が放置されると貧困が広がり、結果的に社会全体が不安定になります。
所得の再分配は、社会全体を守るための仕組みです。
経済の安定化
不況期には企業の利益や給料が減りますが、税金の負担も軽くなります。
家計に残るお金が増えれば、景気の冷え込みもやわらぐのが一般的です。
好況期には利益や給料が増えますが、納める税金も増えます。
結果として手元に残るお金が減り、購買力がおさえられて景気の過熱を防げます。
このように、税金は「不況期の支え」と「好況期のブレーキ」としても働いているのです。
中学生にも関係がある身近な税金の種類に違いがあるのは知ってる?

所得税
高校生以上(15歳以上で義務教育修了者)で、年間103万円を超える収入を得た場合に納めるのが所得税です。
収入が多い人ほど税率が高くなる「累進課税(るいしんかぜい)」という仕組みが導入されており、公平に負担するように工夫されています。
中学生でも家業の手伝いで対価が年間103万円を超える場合は、所得税の対象となることがあります。
住民税
住民税は、私たちが住んでいる市区町村や都道府県に納める地方税です。
前年の所得をもとに 2つの区分で計算されます。
・均等割(きんとうわり)
住んでいる人みんなが一律で負担します。地域に住むための「会費」のようなものです。
・所得割(しょとくわり)
収入に応じて納める税額が変わります。収入が多いほど負担も増える仕組みです。
消費税
消費税は買い物をするたびに支払う税金で、税率は10%が基本です。
たとえば、100円のジュースを買うと10円の消費税がかかり、支払う金額は110円になります。
消費税は、買い物をするすべての人が支払う税金です。
そのため、中学生でもお菓子やゲームなどを買うときに消費税を払っています。
みなさんにとって、もっとも身近な税金と言えるでしょう。
その他の代表的な税金
税金にはほかにもたくさんの種類があります。ここでは代表的な税金を紹介します。
・相続税
家族などが亡くなったときに残された財産を受け継ぐときにかかる税金です。
財産は現金だけでなく、土地や家、株式なども含まれます。
大きな財産が一部の人に集中しないようにするための税金と考えるといいでしょう。
・固定資産税
土地や家など、不動産を持っている人に毎年かかる税金です。
所有している限り支払わなければいけません。
固定資産税は地域の道路整備や上下水道、公園の管理などに使われる大切な財源です。
・法人税
会社が得た利益に対してかかる税金です。
教育や社会保障などの公共サービスに使われています。
会社のためだけに利益を得るのではなく、社会の一員として責任を果たす仕組みです。
いまさら聞けない!税金はどうやって払うの?

給料から引かれる
最も身近でわかりやすいのが、給料から自動的に税金が引かれる「天引き(てんびき)」です。
会社員であれば、お給料を受け取る段階で所得税や住民税が差し引かれています。
納め忘れや手続きの手間がなく、スムーズに税金を支払えるのが特徴です。
給料の明細を見ると「所得税」「住民税」といった項目が記載されており、どのくらい税金が引かれているのかを確認できます。
自分で申告する
会社員ではなく自営業やフリーランスで働く人は、税金を自分で計算して納めなければなりません。
これを「確定申告(かくていしんこく)」といいます。
収入から経費を差し引いた金額に応じて支払う税金が決まります。
確定申告は、収入と税金の関係を整理するためにも欠かせない手続きです。
買い物時に上乗せされる
買い物をしたときに税金が上乗せされる仕組みです。
購入金額に応じて税金を負担します。
たとえば、ゲームやお菓子を買うときには消費税が含まれるため、中学生のみなさんもすでに税金を納めています。
税金はどこにいくら使われてる?金額も詳しくチェック!

教育に使われる税金
税金が使われている大きな分野のひとつが教育です。
国や地方公共団体の1年間(4月から翌年3月まで)の支出を歳出といいますが、国の歳出では「文教および科学振興費」に 5兆6,560億円(歳出全体の約5%)が使われています。
この予算には、公立小・中学校の先生の給料や校舎・体育館の建設費、海洋開発などの科学研究費も含まれます。
東京都は1兆478億円(歳出全体の約11%) で、そのうち約53%は公立小・中学校の運営費です。
児童・生徒ひとりあたり年間100万円以上の公費が投じられています。
教育費は、すべての子どもが平等に学べる環境を守るための費用です。
私立学校にも補助金が支給され、高校1校あたり約2億9千万円が助成されている例もあります。
公共事業に使われる税金
国の歳出は 6兆858億円(全体の約5.4%) が公共事業に充てられています。
道路や橋、上下水道の整備など、社会基盤を整備するために欠かせない歳出です。
東京都でも 9,989億円が都市整備費として計上されています。
地震や台風で電柱が倒れるのを防ぐだけではなく、見通しの良い街並み作りを目指す無電柱化事業は、特に大きな取り組みです。
社会保障に使われる税金
歳出の中で、もっとも大きな割合を占めるのが社会保障です。
国の歳出は 38兆2,938億円が社会保障関係費に使われています。
内訳の中心は年金(約13兆6,916億円)と医療費(約12兆3,368億円)です。
合計で7割近くが高齢者を支えるために使われています。
東京都でも 1兆7,563億円 が福祉・保健に使われています。
子育て支援や障害者施策、高齢者の健康を守る取り組みなどが中心です。
少子高齢化が進む現状では、ますます重要な分野になっていくでしょう。
これで安心!中学生が税金の作文を書くときのヒント
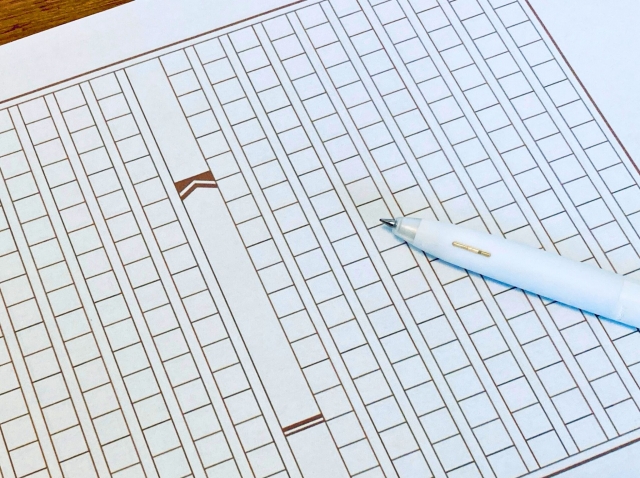
税金関する作文もポイントを押さえれば難しくありません。
まずは、身近な体験や気づきを入口にしてみましょう。
・通っている学校の机や椅子も税金で買われている
・道路や信号も税金で整備されている
など
このように普段の生活に結びつけると具体的でわかりやすい文章になります。
次に、テーマをひとつに絞って深く書くことを意識しましょう。
税金の使い道は幅広いですが、自分が興味を持った分野に集中した方が説得力が増します。
作文の流れは下記を参考にしてみましょう。
1.自分の体験や疑問を書く
2.資料や学んだ内容で根拠を示す
3.そのうえで「だから私はこう考える」とまとめる
このような三段構成にすると読みやすくなります。
最後に、「未来に向けて自分はどう考えるか」を書きましょう。
単なる説明文ではなく、自分らしい意見を取り入れると作文全体のレベルが上がります。
作文は知識を披露する場ではなく、自分の考えをわかりやすく伝える場です。
身近な気づきと素直な意見を大切にすれば、無理なく書き進められるでしょう。
中学生の疑問をすっきり解決!税金に関するQ&A
Q. 税金を払わないとどうなる?
A. 払わないと法律違反になり、延滞税や財産の差し押さえにつながります。
税金は国民の義務なので無視はできません。期限を過ぎると延滞税が加わります。
それでも払わなければ税務署から督促され、最終的には給料や財産を差し押さえられる可能性があります。
Q. 中学生でも税金を払うことはある?
A. 買い物をするときに消費税を払っています。
ジュースやお菓子を買うとき、値段に含まれている消費税をすでに負担しています。
家業の手伝いのように、中学生でも一定以上の収入を得た場合には所得税がかかることもありますが、もっとも身近なのは消費税です。
Q. 税金は誰が決めているの?
A. 国会や地方議会で法律として決めています。
国の税金は国会で、地方の税金は都道府県や市町村の議会で議論されます。
税率や使いみちについても話し合われ、最終的に法律や条例として定められます。
議員は国民や地域の声を代弁し、税金の集め方や使い方を決めているのです。
Q. 控除って何?
A. 生活に必要なお金を考慮して税金を軽くする仕組みです。
たとえば、病気やケガで医療費が多くかかったときには「医療費控除」が使えます。
また、家族を養っている人は「扶養控除」で税金が減ります。
必要以上に負担が重くならないような工夫と考えればわかりやすいでしょう。
Q. 非課税って何?
A. 非課税とは税金がかからないことです。
奨学金の一部やお祝いのお金など、性質上課税の対象にしないものは非課税とされます。
なお、収入が一定以下の家庭は「非課税世帯」とされ、住民税や所得税などを払う義務がありません。国や自治体の支援制度でも優先的に対象になることがあります。
もっと知りたい中学生必見!税金について詳しく学ぶなら【金融塾MIRADAS】へ

税金の世界はとても奥が深く、年齢や立場が変わると見え方も違ってきます。
作文に活かせるだけでなく、将来の生活やお金の考え方にもつながる重要なテーマです。
「もっと詳しく知りたい!」「実際の数字や事例をもとに勉強してみたい!」と思った方は、【金融塾MIRADAS】をチェックしてみてください。
税金やお金の仕組みを学べる講座や資料がそろっています。
中学生でもわかりやすい言葉で説明してくれるのも大きな特長です。
税金の学習は、社会の仕組みを理解して未来を考える第一歩と言えます。
【金融塾MIRADAS】で一緒に学びを深め、安心して次のステージへ進んでみませんか?