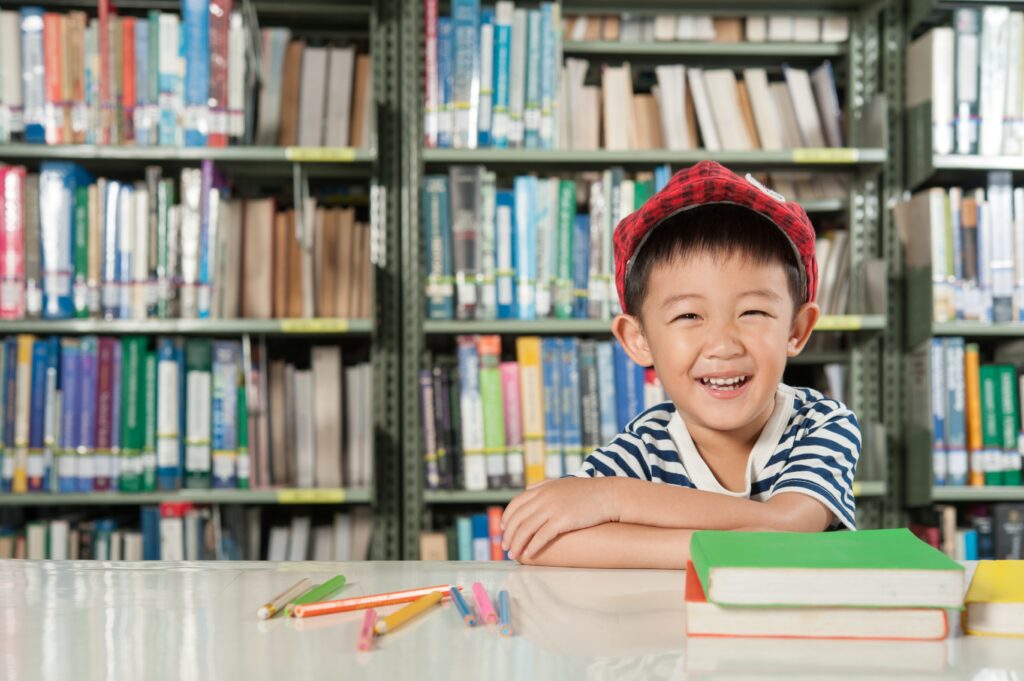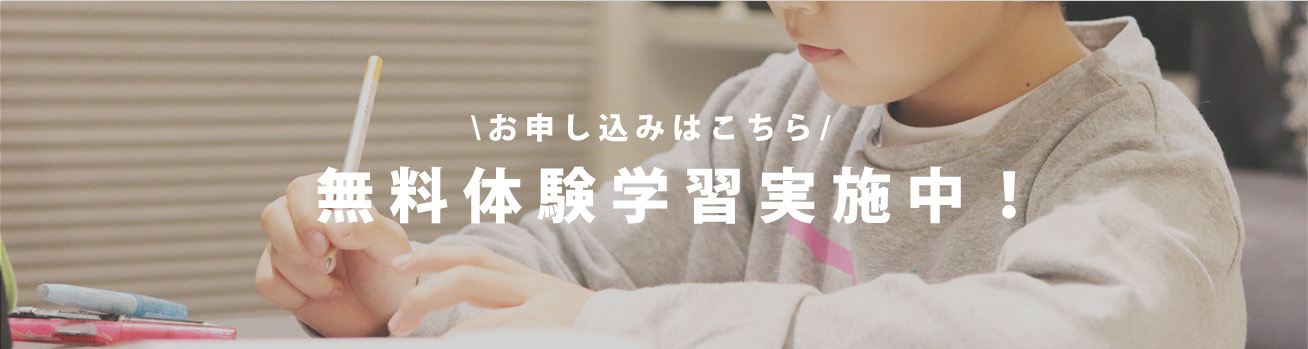「子どもにお金の使い方を教えたいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「お小遣いを渡しても無駄遣いばかりで不安」
そんな悩みを持つ保護者は少なくありません。
キャッシュレスやゲーム課金など、子どもを取り巻くお金の環境は複雑化しており、家庭での金融教育が欠かせない時代です。
とはいえ、学校では十分に学ぶ機会が少なく、どう進めるか戸惑う方も多いでしょう。
この記事では、小学生に必要なお金の勉強を家庭で実践する方法、学年別のステップ、さらに役立つ教材やサービスまで紹介します。
親子で楽しく取り組みながら、将来につながる金銭感覚を育てるヒントをお届けします。
この記事のコンテンツ
なぜ小学生からお金の勉強を始めるべきなのか?

お金の知識や使い方は、生活の中で少しずつ身についていくものです。
キャッシュレス化や成人年齢の引き下げなど社会の変化が進む今、大人になってから慌てて学ぶのでは遅いのです。
小学生のうちから、段階的に金融教育を始めることが将来の安心につながります。
金銭感覚は幼少期から育つ
子どもの金銭感覚は、幼い頃の体験に大きく影響されます。
特に小学校低学年の時期は「お金は使えばなくなる」「同じ金額でも買えるものが違う」といった基本的な仕組みを理解できるようになります。
金銭感覚の基礎を育む絶好のタイミングです。
家庭でできる具体的な方法としては「お小遣い」が挙げられます。一定額を渡し、その使い道を子どもに任せることで、自然に以下のような力が養われます。
- ・欲しいものと必要なものを区別する力
- ・使うか貯めるかを判断する力
- ・予算の範囲でやりくりする力
また、買い物体験も効果的です。
スーパーで「500円以内でお菓子を選んでみよう」と声をかけると、値段や量を比較しながら選ぶ習慣が身につきます。
こうした日常の中の小さな体験が積み重なることで、計画性や我慢する力が育ち、将来の健全な金銭管理につながります。
社会で生きるために必要な「金融リテラシー」
社会で自立して生活するためには、読み書きや計算と同じように「金融リテラシー」が欠かせません。
金融リテラシーとは、お金に関する知識や判断力、そして行動力を指し、日々の消費や将来の資産形成に直結する力です。
金融リテラシーが不足すると、次のようなリスクがあります。
- ・無計画な支出や借金に陥る
- ・クレジットカードや課金サービスでトラブルになる
- ・将来に必要な貯蓄や投資ができない
日本は国際的に見ても金融知識の平均点が低いとされ、とくに若い世代での教育不足が課題となっています。
さらに成人年齢が18歳に引き下げられ、クレジットカードや携帯電話契約などを自分で判断する機会が増えたことから、早い段階での基礎教育が求められています。
| 小学生で学ぶべきこと | 将来の力につながる要素 |
|---|---|
| お金の役割や流れを知る | 社会の仕組みを理解する力 |
| 収入と支出のバランスを考える | 家計を管理する力 |
| 貯蓄の習慣をつける | 将来の備えを作る力 |
小学生のうちに基礎を身につけておくことは、将来の金融トラブルを防ぎ、安心して社会に出るための土台作りになります。
金融庁も推奨する子どもの金融教育
日本の金融教育をリードしているのが金融庁です。
同庁は「金融リテラシー・マップ」を公開し、年齢ごとに学ぶべき内容を体系的に整理しています。
小学生向けには「お金の役割」「お小遣いの管理」「欲しいものの優先順位を考える」といったテーマが含まれており、日常生活に直結する学びを推奨しています。
また、子どもが楽しく学べるように工夫された教材も提供されています。
- ・うんこドリル×金融庁
人気シリーズとコラボした分かりやすいプリント教材
- ・KINYOUランド
ゲーム形式で金融知識を学べるウェブ教材
- ・小学生のためのハッピー・マネー®教室
授業形式で学べる動画教材
これらはすべて金融庁が監修しており、正確性や信頼性が保証されているのが大きな特徴です。
家庭での学習にも使えるため、親子で一緒に取り組むことでより効果的に金融リテラシーを育むことができます。
参照元:金融庁「金融経済教育について」
小学生の学年別:お金の勉強ステップ
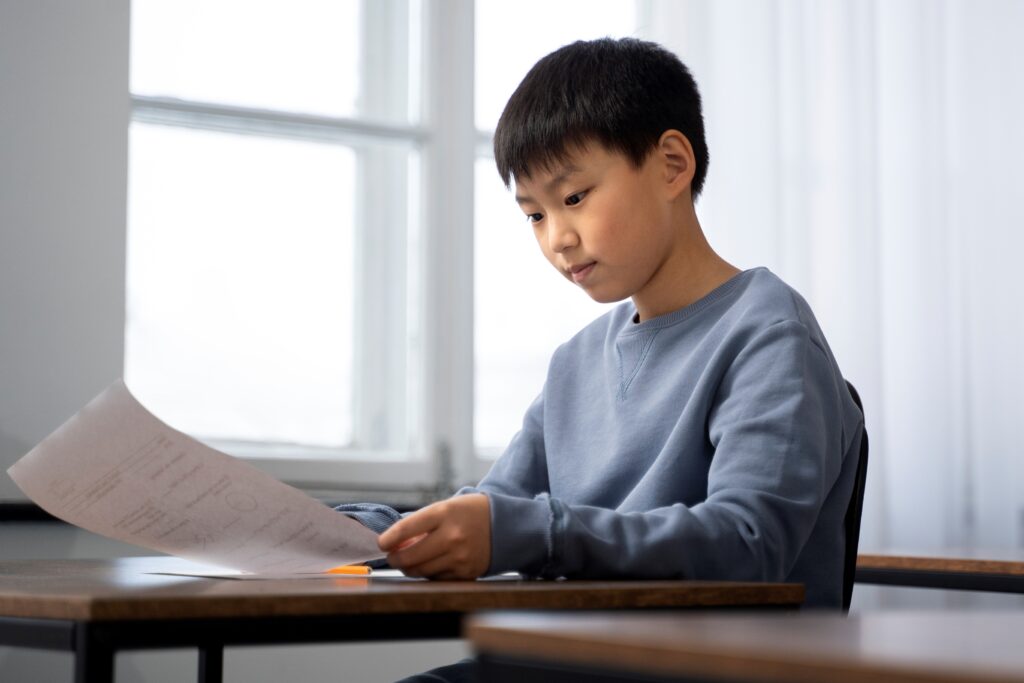
小学生のお金教育は、一律に同じ方法を当てはめるのではなく、成長段階に合わせて工夫することが重要です。
低学年は「お金に触れてみる」ことから始め、中学年は「管理や記録」、高学年では「計画性やキャッシュレス」を取り入れると、自然に金銭感覚が育ちます。
低学年(1〜2年生):お金の種類や使い方を知る
1〜2年生の時期は、まだ「お金は物と交換する道具」という基本を理解する段階です。
数字の大小が分かり始める時期なので、硬貨や紙幣の違いに触れながら「同じ100円でも買えるものは違う」という経験を積むと効果的です。
家庭で取り入れやすい工夫の例
- ・硬貨を種類ごとに並べ、「どれが一番大きい?」「どれが一番価値がある?」と遊びながら学ぶ
- ・スーパーで「100円で好きなものを一つ選んでみよう」と声をかけ、実際に購入体験をさせる
- ・レジでお金を渡させて「お釣りがあるかどうか」を一緒に確認する
| 学びのテーマ | 体験例 |
|---|---|
| お金の種類 | 硬貨を並べて違いを比べる |
| 値段の違い | 同じ100円で選べる商品を比較する |
| 使うと減る感覚 | レジで支払い、お釣りを受け取る |
この時期の学びは「お金そのもの」への興味を広げることが目的です。
数字や計算がまだ不安定な段階でも、体験を通して「お金ってこういうものなんだ」と自然に理解を深められます。
中学年(3〜4年生):お小遣い管理に挑戦する
3〜4年生になると、計算力や判断力が高まり「お金をどう使うか」を考えられるようになります。
この段階では「管理」や「振り返り」の習慣を取り入れると、金銭感覚が一気に成長します。
具体的な取り組み
- ・毎月一定額のお小遣いを渡し、期間内でやりくりさせる
- ・お小遣い帳をつけさせ、何に使ったのかを記録する
- ・欲しいものリストを作り、優先順位を考えさせる
例えば「お菓子に全部使ってしまってゲームが買えなかった」という経験は、失敗ではなく大きな学びです。
「次は貯めて大きな買い物をしよう」と考えられるようになり、計画性が育ちます。
親の役割は「口出しをしすぎないこと」です。
失敗を恐れずに経験させ、その後に「どうしたらよかったかな?」と一緒に振り返ることで、学びが定着します。
高学年(5〜6年生)計画性・貯蓄・キャッシュレスを学ぶ
5〜6年生になると、自分の意思でお金を使う場面が増え、より実践的な力を育てるチャンスです。
この時期は「計画性」と「新しいお金の使い方」を体験させることが効果的です。
実践できる工夫
- ・欲しい物を自分で決め、目標金額を設定して貯金させる
- ・家族行事や旅行の予算を一緒に考え、費用感覚を共有する
- ・少額のキャッシュレス体験(プリペイドカードや交通系IC)で、便利さと注意点を体験する
| 学びの内容 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 目標を立てて貯める | 我慢と計画性が身につく |
| 家族の支出を考える | 金額感覚が育つ |
| キャッシュレス体験 | 管理意識や安全性を学ぶ |
この段階では、ただ「欲しいものを買う」から一歩進んで、「どう使えば効率的か」「将来のために残すにはどうするか」といった思考ができるようになります。
中学生以降の金融教育につながる大切なステップです。
親子で一緒に「ゲーム感覚」で取り組む方法
お金の学びは真面目な説明だけでは子どもが飽きてしまうため、ゲームや遊びを取り入れると効果的です。
楽しく取り組める工夫を通じて、自然に金銭感覚を身につけられます。
おすすめの方法
- ・ボードゲーム
「人生ゲーム」「キャッシュフロー・キッズ」などで収入と支出のバランスを体験
- ・アプリ
「お小遣い帳アプリ」や「ハロまね」で仮想銀行や利息を体験
- ・ロールプレイ
家庭で「お店屋さんごっこ」をして、売る側・買う側を交互に体験
- ・イベント
「キッズマネースクール」など親子で参加できるワークショップ
これらを親子で一緒に楽しむことで、「お金の勉強=難しい」という意識がなくなり、学びをポジティブに受け止めやすくなります。
親が積極的に関わり「なぜこの選択をしたの?」と会話を広げると、子どもの考える力も一段と深まります。
小学生が家庭でできるお金の勉強

家庭は子どもにとって一番身近な金融教育の場です。
お小遣い帳や欲しいものリスト、買い物体験や家族会議など、日常生活に小さな工夫を加えることで、学校だけでは学べない実践的なお金の感覚を自然に育てることができます。
お小遣い帳をつけて収支管理を学ぶ
お小遣い帳は「入るお金」と「出ていくお金」を記録し、自分のお金の流れを見える化する手段です。
記録を続けることで「今月は使いすぎた」「来月は残そう」と自分で気づけるようになり、自然と計画性が身につきます。
活用のポイント
- ・使ったらその日のうちに記録する
- ・月末に親子で一緒に振り返る
- ・「なぜ使ったか」を簡単にメモする
こうした取り組みを重ねると、子どもの意識に変化が表れてきます。
| 学びの効果 | 具体的な姿勢の変化 |
|---|---|
| 記録習慣 | お金を使うたびに振り返る意識が芽生える |
| 可視化 | グラフや数字で支出の偏りがわかる |
| 自己管理力 | 欲望だけでなく計画的に使おうとする |
最近ではアプリ版もあり、収支を自動でグラフ化してくれるものも人気です。紙でもデジタルでも構いませんが、「続ける仕組み」を作ることが成功のポイントです。
欲しいものリストで「優先順位」を考える
子どもは「欲しいもの」が次々と出てきますが、そのすべてを手に入れることはできません。ここで役立つのが「欲しいものリスト」です。
ノートや付箋に書き出し、「すぐに欲しい」「待てる」「本当に必要か」と分類すると、優先順位を考えるトレーニングになります。
取り組み例
- 1.欲しいものを3〜5点書き出す
- 2.値段・使用頻度・必要性を比較する
- 3.親子で「どれから買うか」を話し合う
このプロセスを通じて、子どもは選び方の基準を少しずつ身につけていきます。
| リストに書く基準 | 学べること |
|---|---|
| 値段 | 価格と価値を比べる力 |
| 使用頻度 | 長く使えるかどうかを考える |
| 必要性 | 欲望と必要の違いを意識する |
「どうしてそれを一番に選んだの?」と親が問いかけることで、子どもは自分の基準を言葉にできるようになり、判断力が深まります。
スーパーや買い物体験を活用する

実際の買い物は最高の金融教育の場です。スーパーに行く際、「500円以内で選んでみよう」と条件を出すと、自然に値段や量を比較して選ぶ習慣が身につきます。
工夫できる体験
- セール品と通常品を比べて「どちらが得か」を考える
- 同じ商品でも容量・単価を比較する
- レジで支払いとお釣りを一緒に確認する
これらの体験を通して、お金は単なる数字ではなく「生活を選ぶ道具」であることに気づきます。
| 体験の内容 | 育つ力 |
|---|---|
| 値段を比べる | 比較判断力 |
| 予算内で選ぶ | 優先順位をつける力 |
| 支払い体験 | 計算力・責任感 |
数字の計算だけでなく、日常の中で「価値をどう判断するか」を学べるのが、買い物教育の大きな強みです。
家族会議でお金について話し合う
家庭でお金をオープンに話す「家族マネー会議」は、子どもにとって大きな学びの場になります。
月1回でも「今月のお金の使い方」を家族で共有すると、子どもは自分も家計の一員だと感じられます。
進め方の例
- 1.食費・習い事・娯楽などの支出を簡単に書き出す
- 2.「必要な支出」「減らせる支出」を話し合う
- 3.来月の目標を決める(例:お菓子代を減らして貯金に回す)
こうした会議を継続すると、子どもはただ話を聞くだけでなく、自分の意見を言葉にする練習にもなります。
| 会議の効果 | 子どもの変化 |
|---|---|
| 価値観の共有 | 親のお金の考え方を学べる |
| 意見を述べる | 自分の考えを伝える練習になる |
| 将来設計力 | 計画的に使う発想が芽生える |
「親が決めて伝える場」ではなく「家族で一緒に考える場」とすることが、子どもの主体性を育てる鍵になります。
小学生におすすめの教材・サービス

金融教育を効果的に進めるには、身近に使える教材を上手に取り入れることが大切です。
プリントや本、漫画、アプリ、ゲーム、公的機関の教材まで幅広く揃っているので、子どもの学年や興味に合わせて活用すれば、楽しみながら学びを深められます。
プリント教材で基礎を学ぶ(無料・有料)
プリント教材は、低学年から始めやすい金融教育の定番です。紙に書いたり切ったりする体験を通じて、「数字」や「お金の種類」が自然に身につきます。
〇お金のおもちゃプリント(すたぺんドリル)
硬貨や紙幣のイラストを切り取って「お店屋さんごっこ」ができる教材で、遊びながら硬貨の違いを理解できます。
〇金融経済教育推進機構(J-FLEC)の教材
金融庁などが監修するワークシートで、お金の使い方や貯め方をクイズ形式で学べます。
| 教材の種類 | 特徴 | 対象 |
| 無料プリント | 手軽に印刷でき、繰り返し遊べる | 低〜中学年 |
| 有料ワークシート | カリキュラム的に体系化 | 中〜高学年 |
「遊び」と「学び」を結びつけやすいため、家庭のちょっとした時間に取り入れると効果的です。
本で学べる「お金の仕組み」
読書は知識を体系的に整理できる手段で、親子で一緒に取り組みやすい方法です。金融の基礎から実生活で役立つ知識まで、幅広いテーマの本が出版されています。
〇『子どもにもできる資産形成 いますぐ知りたいお金のしくみ』
図解やイラストを交え、「使う・貯める・増やす」をわかりやすく解説しています。
〇小学生向けマネー本まとめ
年齢や性格に合わせて選べる、おすすめ本10選を紹介しています。
家庭で読むときは「どんなことが役立つと思った?」と話し合うと、知識の定着に加えて親子の価値観も共有もできます。
漫画で楽しく理解する金融知識
漫画は子どもが抵抗なく手に取りやすく、物語を通じてお金の概念を楽しく理解できます。
〇『マンガでわかる お金の使い方・貯め方・増やし方』シリーズ
ストーリー形式で理解が進み、記憶にも残りやすいです。
〇『学校では教えてくれない大切なこと③ お金のこと』
ユーモラスに貸し借りやリスクも学べる一冊です。
〇金融教育おすすめ漫画まとめ
複数の選択肢から、子どもに合った一冊を見つけやすいです。
| メリット | 効果 |
| 読みやすい | 勉強が苦手でも入りやすい |
| 記憶に残りやすい | ストーリーで印象的に学べる |
読書習慣がない子でも「漫画なら自分から読む」というケースが多く、学びの入り口として最適です。
アプリを使った金銭管理の練習
アプリは、収支管理を「見える化」し、ゲーム感覚で続けやすいのが特徴です。特にデジタルに慣れた世代には効果的です。
〇ハロまね – 親子で学ぶ金融教育アプリ
三井住友カード提供で、お小遣い管理に加え、仮想銀行や利息体験が可能です。
👉 App Store – ハロまね
〇manimo – 親子で使えるマネーアプリ
プリペイドカードを活用し、「稼ぐ・貯める・使う」を実践できます。
〇教育アプリ特集
最新の教育アプリを比較検討できる便利なまとめになっています。
アプリは「結果がグラフで出る」ため子どもも達成感を得やすく、継続的な学びにつながります。
ボードゲームや体験型教材で遊びながら学ぶ
ボードゲームは、お金の流れや意思決定を「体験」として学べる教材です。親子で楽しめる点も大きな魅力です。
〇キャッシュフロー・フォー・キッズ
投資や資産形成の基礎を遊びながら体験できます。
〇人生ゲームやモノポリー
お金を増やす・減らすを疑似体験できる定番ゲームです。
〇神奈川県の教材「見えるお金と見えないお金」
公的教材で社会的なお金の仕組みも理解できます。
| 特徴 | 学べること |
| 遊びながら学習 | 判断力・計画性 |
| 家族で楽しめる | 会話が生まれる |
| 公的教材もあり | 社会的な仕組みも理解 |
ゲームを通じて「お金は選択によって動くもの」という実感を得られます。
金融庁の公式教材・動画を活用する
公的機関が提供する教材は、正確で信頼性が高いのが魅力です。無料で利用できる点も家庭学習に適しています。
〇うんこお金ドリル(金融庁)
子どもに人気のキャラクターで楽しく学べます。
👉 知るぽると – うんこお金ドリル
〇小学生のためのハッピー・マネー教室(動画教材)
授業形式の動画で、家庭でも視聴しやすいです。
〇金融リテラシーマップ(金融庁監修)
年齢別に必要な知識が整理されていて、何を学べば良いか指針に使えます。
これらは学校現場でも利用されており、家庭でも安心して使える教材です。学んだあとは感想を共有し、家庭の価値観に沿った学びにつなげるのが効果的です。
小学生のお金の勉強は家庭から始めよう

小学生のお金教育は、特別な教材がなくても家庭で始められます。
お小遣い帳をつけて収支を見える化したり、欲しいものリストで優先順位を考えたり、日常の買い物や家族でのお金の話し合いを通じて、自然に金銭感覚が育まれます。
こうした習慣は、将来の判断力や計画性につながり、子どもの自立心を支える大切な基盤となるでしょう。
さらに体系的に学ばせたい場合には、専門スクールの活用も有効です。MIRADAS(ミラダス) は、小学生から楽しみながら実践的に金融リテラシーを学べる金融塾です。
企業分析やバーチャル投資を取り入れた独自のカリキュラムで、知識だけでなく「考える力」「行動する力」も育てられます。
まずは、お気軽にご相談ください。